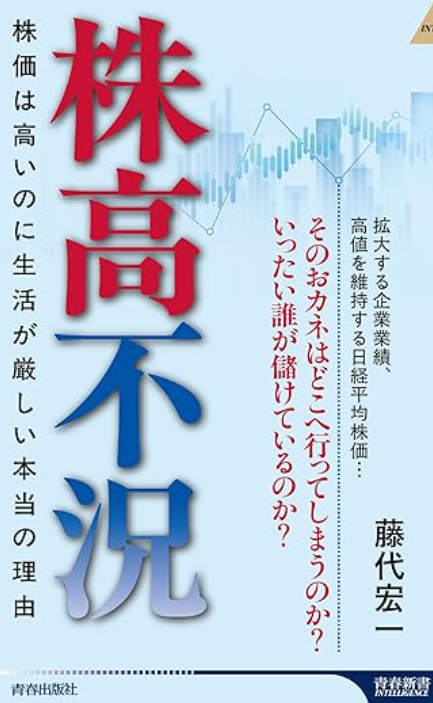
最後に批判以外の話を追記しよう。インフレレジーム下ではインフレ耐性が強い株式資産を保有しないと、インフレ下の格差拡大に取り残されてしまうと説く『株高不況』が大ヒットになった。
普通は2022年の米国のように、物価目標を超えるインフレになったら金融政策も引締め方向に転換するため、「インフレでは名目値であるEPSが膨らむ」という論理で株を買ってインフレヘッジしようとすると、インフレ退治プロセスの衝撃に晒されることになる。
ところが日本では中央銀行が実質的に物価目標を放棄したため、家計にとっての資産防衛の合理性は例外的に高かったし、その過程でのストレスは例外的に低くなった。そもそもなぜ物価目標が存在することが経済にとってプラスかというと、それがないなら中央銀行が発行する紙幣など紙くずにすぎないまさに労働者が目まぐるしく変わる物価を追い掛けたり資産防衛に時間を割くと本業の生産性が落ちるからであるが、背に腹は代えられない。
編集部より:この記事は、個人投資家Shen氏のブログ「炭鉱のカナリア、炭鉱の龍」2025年9月5日の記事を転載させていただきました。










































