このグループが注目される理由は、人間や動物、植物などのような複雑な細胞を持つ生き物(真核生物)の祖先に非常に近いとされる古細菌の仲間だからです。
言い換えれば、私たちの遠い親戚にあたる微生物だと考えられています。
この微生物が生きている証拠を調べるため、研究チームはシベリアの北東部にある「コリマ低地」の永久凍土を調査場所として選びました。
この地域には「Kon’kovaya層」と呼ばれる、約10万〜12万年前に凍りついたまま現在に至る、海が起源の永久凍土の層があります。
もしこの層の中でプロメテアルケオタが「今も生きた状態」で存在しているなら、それは微生物が極寒環境でも極端に長い時間生き延びられる証拠になります。
DNAを修復しながら10万年生き続ける
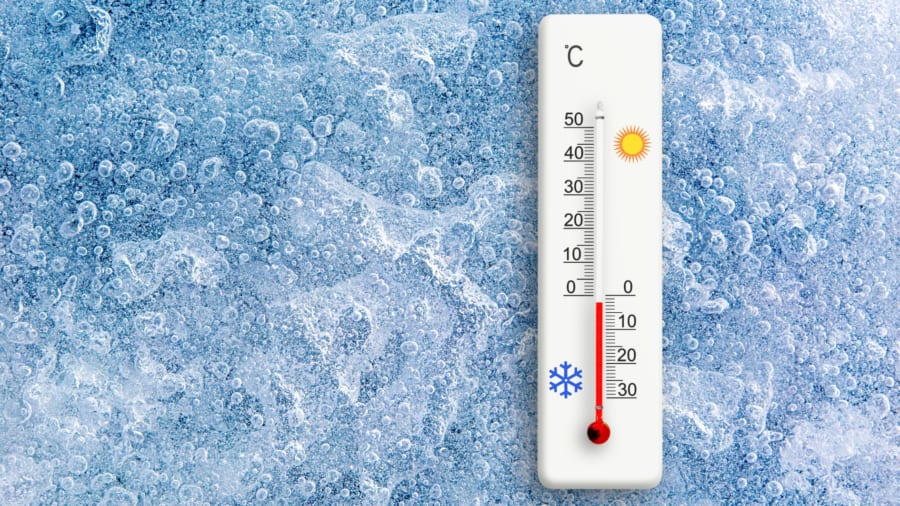
研究チームは、シベリアのコリマ低地にある「Kon’kovaya層」と呼ばれる永久凍土を調べることにしました。
この層は、約10万年〜12万年前に海水が入り込んでその後凍りつき、そのまま現在まで変わらない状態を保ってきた特殊な環境です。
もしここで今も生きている微生物が見つかれば、それは「氷の中で何万年も生き延びられる」ことを示す決定的な証拠となります。
研究チームはまず、このKon’kovaya層から土を取り出して、「微生物のDNA」を採取しました。
DNAとは、生物の遺伝情報が書き込まれた非常に小さな分子で、生き物が生きている間は細胞の中に大切に保管されています。
しかし、生物が死んで細胞が壊れると、DNAは細胞の外に出て土や水の中に漂い、徐々に傷んでいきます。
そのため研究チームは、生きている微生物が細胞の中で守っているDNA(iDNA)と、死んだ微生物が細胞外に放出した傷んだDNA(eDNA)を区別して調べることにしました。
イメージとしては、「頑丈な金庫の中に保管された貴重な書類(細胞内DNA)」と、「金庫が壊れて外に飛び散り、時間と共に傷んでしまった書類(細胞外DNA)」のような違いです。














































