たまたま博士課程2年だった1976年に「マンハイム全集」全6巻が完結して、その知識社会学や社会計画論の全貌に触れることができた。
とりわけ主著の『変革期における人間と社会』の後半に収められた「現代の診断」(Diagnosis of our Time)は文字通り精読した。なぜなら、マンハイムが第二次大戦中の具体的な問題を取り上げ「診断」して、いわば「処方箋」を書くことまでを社会学の課題として実践したからである。
社会学を武器として社会の将来図を描くことは、都市論のうちコミュニティ研究を志していた私にも大きな刺激となった。いずれ私も「現代の診断」(Diagnosis of our Time)が書けるようになりたいという思いを強くした。
37年後に『「時代診断」の社会学』を刊行した
そしてそれから37年後の2013年に、自己流だがその観点から『「時代診断」の社会学』が刊行できた。
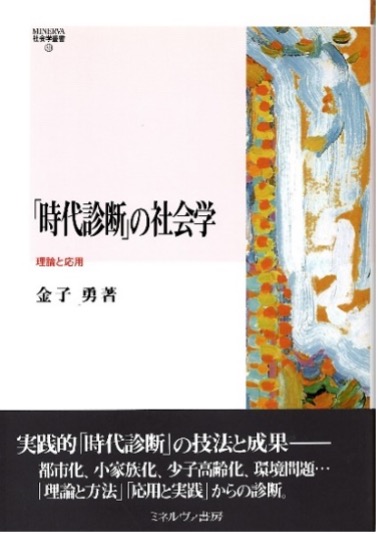
体裁は前半が理論編、後半が実証編
これは6月1日に取り上げた『社会学的創造力』、7月20日の『社会分析』と同じく、前半を理論編、後半を実証編とした。
理論編では、「計画とは、社会の全機構と生きた構造に関する知識に基づいて、社会という器械装置に見出される欠陥の根源を意識的につくこと」(マンハイム、1935=1976:104)を受けて、特定のテーマに即した将来像を描こうとした。
診断とは何か
診断とは、選択したテーマの現状を調べて、全体として標準化された基準から判定する技法を含み、最終的に価値判断を下し、社会計画につなぐことである。
そこにはたとえば医学者のベルナールが力説する「『事実』は必要な材料である。真に科学を構成するのは、実験的推理、即ち学説による『事実』の活用である」(ベルナール、1865=1970:51)から、観察された事実に基づいて判断して、計画につなげることになる。
科学的知識に関する基本的規準
科学的知識に関してパーソンズは、①経験的妥当性、②論理的明晰性ないし個々の命題の正確さ、③命題間の相互的含意の論理的一貫性、④関与している「いくつかの原理」の一般性をあげている(パーソンズ、1951=1974:334)。














































