「ウクライナは停戦に合意した後、徐々に自国を『軍事ハリネズミ』つまり誰も侵略したがらないような厄介な国に変えていくだろう。中規模の国家であれば、非常に危険な敵対者からでも、自らを守ることができる。ウクライナは将来、防衛力を高められるが、国として社会として侵攻前とはかなり違う姿になるだろう。高い税金と軍事費、長期の兵役義務などを伴うイスラエルのような国になろう。しかし、ウクライナは防衛できる。彼らはそれを既に証明したのだ」。
ライター氏は、ロシアが短期の一方的な勝利を収められず、戦線も大きく動きにくくなった時点で、ウクライナとのパワー・バランスはある程度明確になり、ウクライナがロシアに手痛い打撃を与えられる状態では停戦合意の違反も起きにくい、と判断したようです。これは開戦直後の「イスタンブール・コミュニケ」とならんで、ウクライナ戦争を終結させる「失われた機会」だったのかもしれません。
こうしたチャンスを逃してしまうと、戦争は「サンクコストの誤謬」すなわち「これまでの犠牲を無駄にできない」という心理も強く働くようになる結果、交戦国は戦闘を終わらせることより続けることに固執しやすくなります。
停戦の継続パターン
戦争のタイプと停戦の継続性についても、研究は進んでいます。主なものとしては、ヴァージニア・ペイジ・フォトナ氏(コロンビア大学)の著書『平和の時間―停戦合意と平和の継続―』(プリンストン大学出版局、2004年)があります。
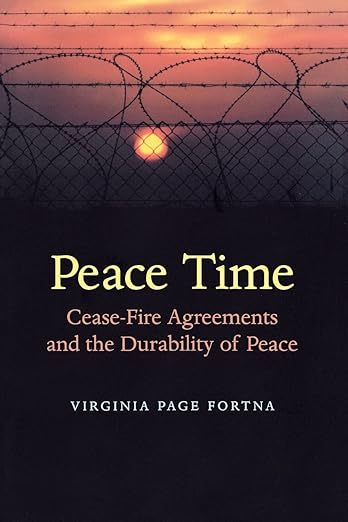
彼女によれば、終わった戦争が再燃するかどうかは、その終わり方次第だと主張しています。ここでは、その主要命題と事例を紹介します。
「平和(停戦)を維持することは、長く費用もかかり、明確な勝者で終わり、どちらの国家の存続も脅かさない戦争の場合により容易になる」(Peace Time、p. 119)。
「停戦が脆く、戦闘が再開しやすいのは、長期の紛争状態にある隣国同士が、特に、膠着状態に終わった、賭けるものが高いわりには高くつかなかった戦争を行った場合、次の戦闘を防ぎにくくなる」(p. 112)。











































