つまり、10種類を組み合わせることで互いの力が補い合い、相乗効果が生まれたのです。
この戦略は複数の薬でウイルスの逃げ道をふさぐ「カクテル療法」に似た、遺伝子版の新しいアプローチと言えます。
副作用についても細胞実験の範囲で慎重に確認されました。
10-ISGカクテルを導入した細胞では、インターフェロンを直接加えたときのような強い炎症反応は見られず、細胞の生存率も通常と変わりませんでした。
つまり、余計な“警報”を鳴らさずに必要な防御だけを静かに働かせることができたのです。
この技術が生きた体でも通用するかを確かめるため、次にマウスとハムスターで動物実験が行われました。
まずマウスには致死量のインフルエンザウイルスA型を感染させ、感染の1日前に10-ISGカクテルを投与しました。
3日後には肺内のウイルス量が大きく低下しましたが、生存率の大幅な改善までは達成できませんでした。
今後は投与タイミングや量、遺伝子の組み合わせの改良でさらなる効果向上が期待されています。
ハムスターの実験では強毒株のSARS-CoV-2を用い、感染の1日前に同じmRNA薬を鼻から投与しました。
薬を受けたハムスターは体重の減少がほとんどなく、肺内ウイルス量も少なく、肺の組織ダメージも軽減されました。
この結果は、事前にmRNA薬を使うことで感染後の重症化を抑えられる可能性を示唆しています。
以上のように、10種類の防御遺伝子を一時的に働かせる方法は、ヒト細胞実験と動物実験の両方で多くのウイルスに効果を示し、広域防御戦略の第一歩となると期待されています。
パンデミックに備える“体内防衛薬”
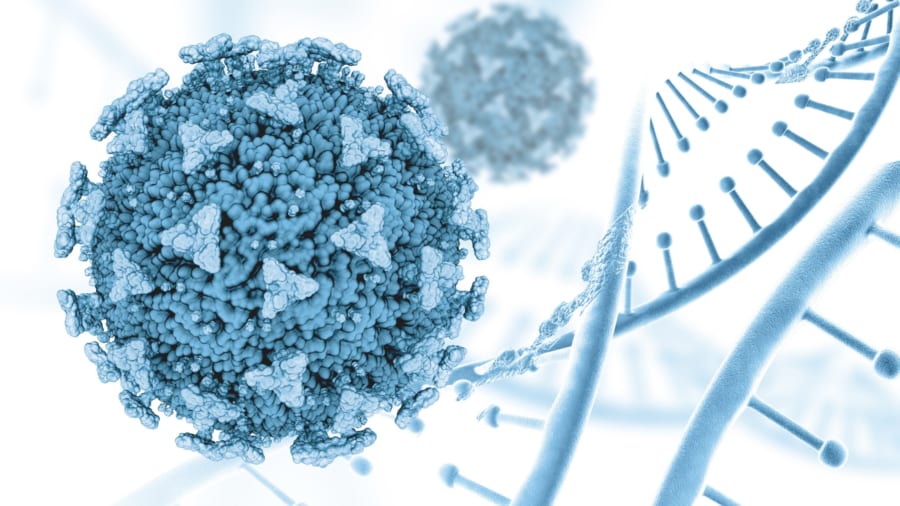
今回の研究で開発されたmRNA薬は、これまで困難とされてきた「広く効く抗ウイルス薬」の実現に向けた新しい可能性を示しています。
これまでの医療では、インフルエンザにはインフルエンザ薬、コロナにはコロナ治療薬というように、ウイルスの種類ごとに個別の薬を用意する必要がありました。













































