ですがボルン・オッペンハイマー近似では電子に比べて原子核は非常に重く動きも遅いため、シュレーディンガー方程式などで電子の動きを考えなければならないときには「とりあえず原子核は停止していると考えても問題ない」とされます。
ボルン・オッペンハイマー近似で導き出される数値は厳密な意味で真実ではありませんが、計算の手間というデメリットを、計算簡略化のメリットが上回るのです。
アインシュタインの相対性理論に比べれば、若干、見劣りするかもしれません。
しかし重要な発見なのは確かです。
ボルン・オッペンハイマー近似を誰かが考え付かない限り、人類はシュレーディンガー方程式をまともに解けなかった可能性があるからです。
しかしオッペンハイマーの業績はこれ1つだけではありません。
実は、オッペンハイマーはブラックホール理論における、先進的な理論をうみだしていたのです。
そしてこちらは便利ツールではなく、正真正銘ノーベル賞級となっています。
オッペンハイマーのブラックホールに関わるノーベル賞級の業績
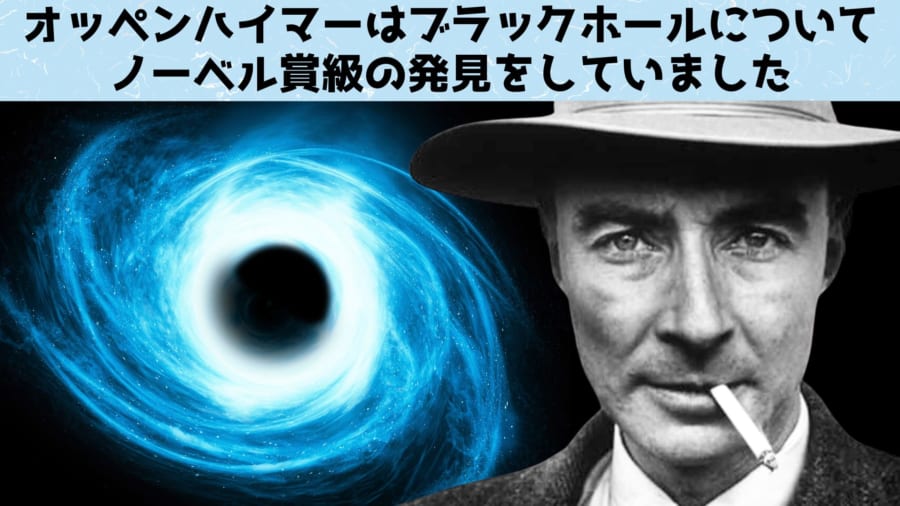
オッペンハイマーにはノーベル賞受賞歴はありません。
ノーベル賞は生きている人間にだけ与えられる賞なので、いくら優れた業績を残しても、死後に評価された場合は対象外となってしまうからです。
オッペンハイマーは1939年、ブラックホールがどんな条件で形成されるかという、極めて先進的な理論を発表しました。
ブラックホールは簡単に言えば、重さに耐えきれず時空に開いた穴が開いた状態です。
通常、質量を持つ物質が大量に存在すると、それらは重力によって互いに引き合い、太陽のような巨大な星が誕生します。
すると星の内部は重力によって大きな圧力がかかることになります。
太陽などでは、星の内部にかかる圧力を核融合による熱が支えているため、星の大きさは安定に保たれています。











































