20世紀初頭は量子理論に革命が起きていた時期であり、新たな理論が新たな偉人と一緒に次々に登場しました。
残念なことに、オッペンハイマーは彼らと同クラスの物理学者ではありませんでした。
しかしその主な原因は、オッペンハイマーの能力とは別にありました。
オッペンハイマーが生まれた時期は、1904年です。
一方、アインシュタインは1879年、シュレーディンガーは1887年、ハイゼンベルグは1901年、パウリは1900年、ディラックは1902年となり、全員オッペンハイマーよりも早く生まれています。
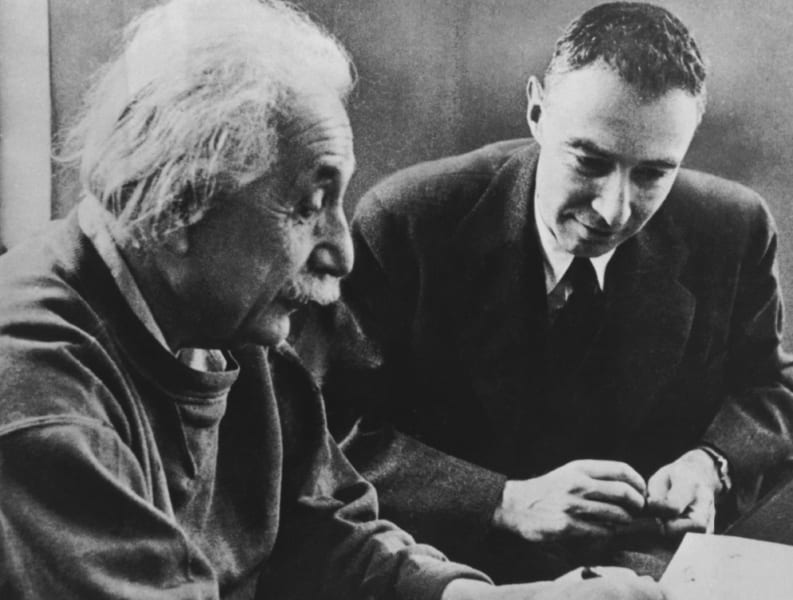
「生まれた年が少し遅いだけで業績に差が出るのか?」と疑問に思うかもしれません。
しかし新たな量子理論が次々に現れる革命期には、ほんの数年、生れ年が遅うだけで大きな影響が出ます。
実際、オッペンハイマーが博士号を取得し物理学者として独り立ちした時期は、多くの量子理論が出そろっており「応用の時代」となっていました。
(※米国の科学哲学者トーマス・サミュエル・クーンの言葉を借りれば「掃討作戦」の時代となるでしょう)
しかしそんな応用の時代でも、オッペンハイマーは優れた業績を残しています。
その1つが、量子力学の教科書にはかならず乗っている「ボルン・オッペンハイマー近似」です。
(※もう1つのブラックホールに関わるノーベル賞級の業績については次ページを参照)
なんだか難しそうな名前ですが、極論するなら「円周率に3.14ではなく3を使う方法」となります。
というのもボルン・オッペンハイマー近似は計算の負担を減らす、非常に便利な方法だからです。
原子や分子の挙動をシュレーディンガーの方程式で正確に表すには、原子核と電子の両方の運動について考えなければなりません。
現実に存在する原子は、原子核も電子も常に動いているからです。











































