日本プロ野球(NPB)も2018年から監督のリクエストによるリプレイ検証を導入し、テレビ局の中継映像を利用している。しかし、2023年5月28日の楽天対日本ハム戦では、タッチアップの離塁を確認する映像がなく判定変更ができなかった事例があった。これは、中継映像のみを判定材料とする際の限界を示した例といえる。
こうした背景からも、FIFA推奨サイズである105m×68mのピッチを持つサッカーで、中継映像だけをVARに流用するのは現実的ではない。
加えて、ボールにチップを内蔵するゴールラインテクノロジー(GLT)の導入も有効な選択肢となる。これはVARよりも早く導入された判定補助システムで、ライン上のイン・アウト判定を自動化できる。ただし、スタジアムあたり数千万円規模の初期導入費がかかるため、低コストというよりは、対象判定が限定される分、VARよりも運用が簡素なシステムといえる。
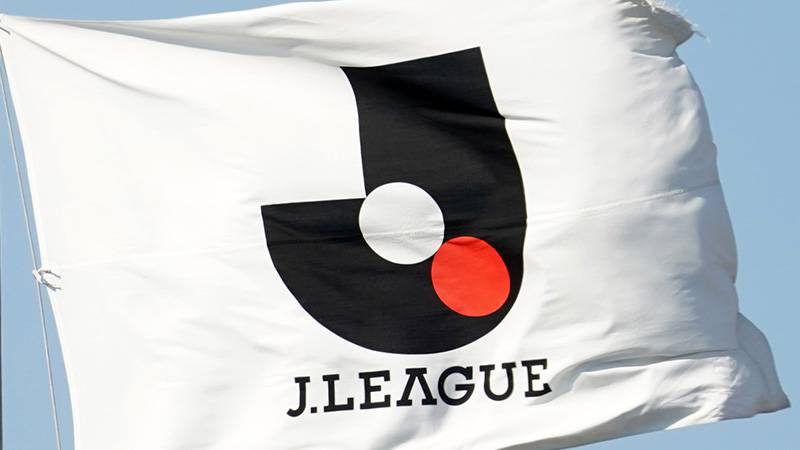
Jリーグ全体での財政支援
Jリーグが将来的にVAR導入のための財政的支援を行う可能性も議論されている。例えば、既存の分配金制度の一部を活用し、J2・J3クラブのインフラ整備を後押しする仕組みを整えれば、リーグ全体の公平性が向上する可能性がある。ただし、これにはクラブ間の利害調整が必要であり、現時点で具体的な補助制度が決まっているわけではないため、実現には時間を要するだろう。
J1での誤審は、VARの運用における人的判断の限界や技術的制約に起因する。一方、J2・J3リーグでは、人材不足、資金面の制約、技術的インフラの不足がVAR導入の障壁となっている。冒頭で示した誤審の議論は、これらの課題を浮き彫りにした。簡易型VARやゴールライン技術の導入、審判の育成、財政支援を通じて、Jリーグ全体での判定の公平性を高める努力が求められるのではないだろうか。













































