相手に対する生理的・非言語的な反応ではプラスの効果が現れても、最終的な好みの部分では同じ階層の相手を選んでしまうのです。
社会階層を超えた壁は心や体に影響を与える
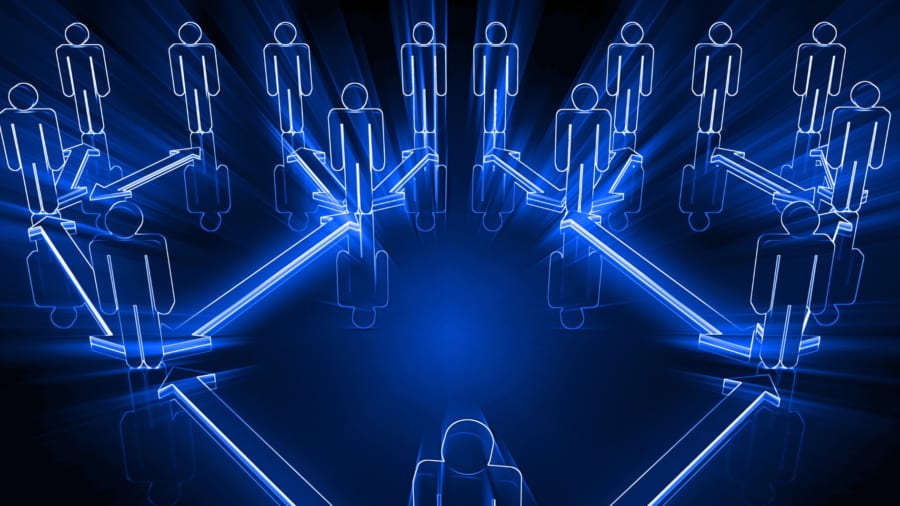
今回の研究で明らかになったのは、社会階層が低い人ほど、相手の気持ちに敏感で、無意識のうちに気を配っているということです。
実はこれ、これまでの心理学の研究でも「そうかもしれない」と言われてきました。
たとえば、社会階層が高い人はお金や教育、立場に恵まれていることが多く、まわりの人や状況にそれほど振り回されることなく、自分の意見をはっきり言える傾向があります。
それに対して、階層が低い人は、社会の中で困難なことに直面することが多くなりがちです。
そのため、人の表情や雰囲気、ちょっとした言い回しなどに敏感になっていきます。いわば「空気を読む力」が自然と育っていくのです。
今回の実験でも、社会階層が低い人は初対面の相手に対しても、自分の心の動きや体の反応を相手に合わせるようにしていました。
これによって、相手もリラックスしやすくなり、会話全体が落ち着いた雰囲気になったのです。
まるで「この人といると安心するな」と感じるような、そんな雰囲気を生み出してくれていたのかもしれません。
不思議なことに、こうした「安心感」があっても、参加者たちが「この人が好き」「また話したい」と思った相手は、やっぱり自分と同じような社会階層の人でした。
たとえ相手がやさしくしてくれていたとしても、「自分とちょっと違う」と感じる相手とは、なかなか仲良くなれないというわけです。
これは、心理学の世界で「似た者同士効果」と呼ばれる考え方とも一致します。
人は、自分と似たような人のほうが安心しやすいし、好きになりやすいという、人間らしい本能とも言えるものです。
研究チームの人たちは、「たった一回の短い交流だけでは、階層を超えて仲良くなるのは難しいのかもしれない」と考えています。











































