沖縄戦での米軍の死傷者は3.9万人、これに特攻による死傷者7700人が加わります。日本軍の兵力(死傷者数)は沖縄戦で11万人ですから、「本土決戦」では5倍以上、利用可能な特攻機も沖縄戦の約2000機のほぼ5倍の約1万機。
単純計算では、米軍の死傷者は沖縄戦の5倍となる約23万人。経験的に、軍隊は3割の兵員が死傷すると戦闘力を失うとされ、仮に予定どおり70~80万人規模の米軍が九州上陸に成功したとしても、追加兵力を投入しない限り占領は困難ということになります。
このように、仮に昭和20年「本土決戦」が勃発したとする場合、米軍の死傷者数は何十万人にも激増し、政変や撤退を招くレベルの世論圧力が発生する可能性が高いのです。日本軍が米軍に対して戦術的勝利を収めるというよりは、米軍の損害・政治的リスクが「本土全面占領」に対して割に合わないと判断させる。
そして、この「高すぎるコスト」こそが、結果として日本にとっての“勝利”を導く。ある意味では、ベトナム戦争に似ており、仮に「本土決戦」が発生したとしても、米軍は“自主的”に撤退せざるを得ない可能性さえあるのです。
これが、簡易シミュレーションにより得られた一つの結論ということになります。
柴山論文──原爆投下の戦略的な意味
このような視点は、関西学院大学・柴山太氏の論文「大日本帝国陸軍はアメリカ軍の本土上陸作戦を阻止し得た!」にも見られます。
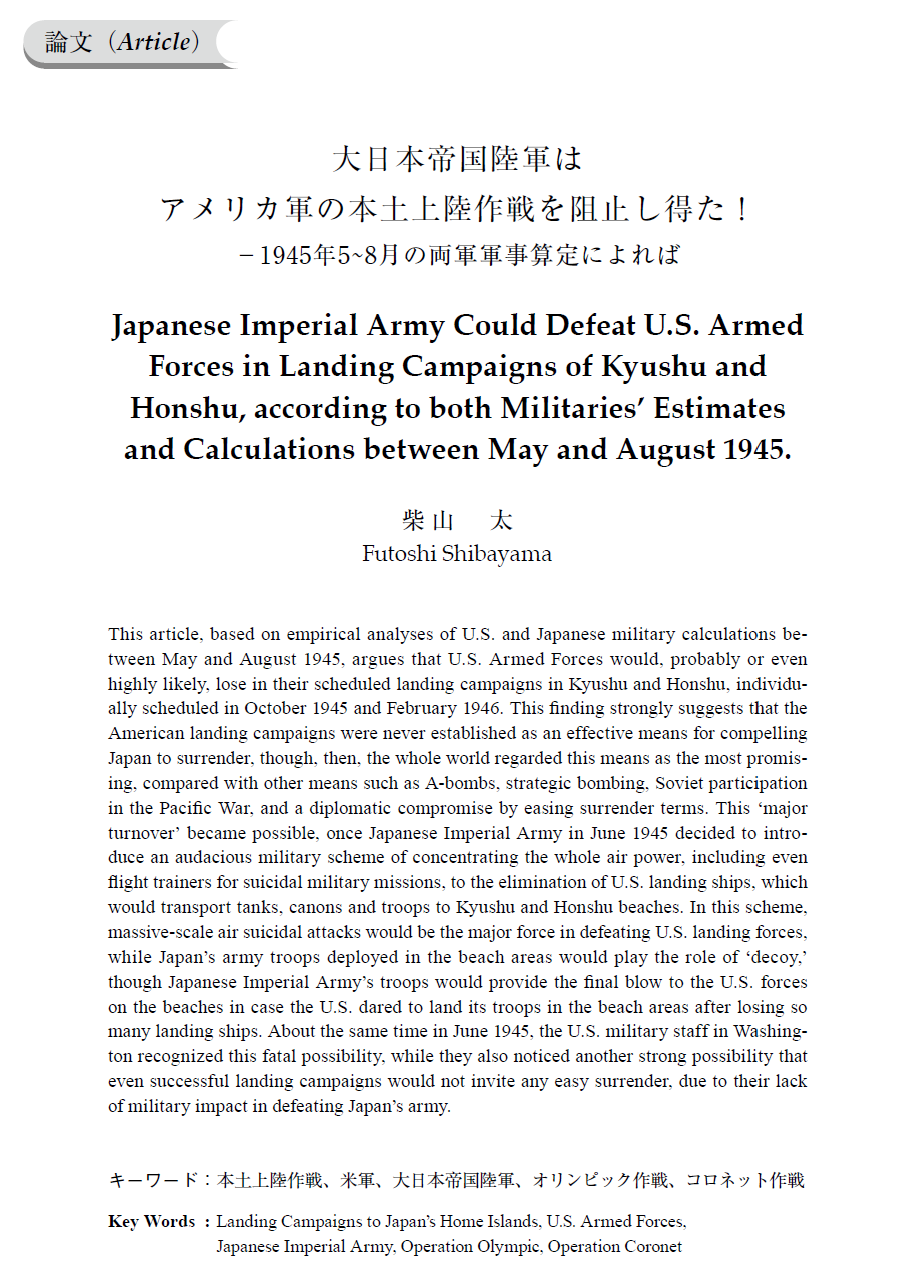
図6 柴山太氏の論文「大日本帝国陸軍はアメリカ軍の本土上陸作戦を阻止し得た!」
この論文のポイントは、そんな検討結果が米軍の原爆使用を強く後押ししたということです。
もしトルーマンを含む政府首脳が、これらの対日上陸作戦の実質的失敗予想を知ることになれば、よりいっそう原爆使用に賭ける姿勢となったことは容易に推察される。またそうなった場合、原爆投下作戦は、自力で対日戦を勝利し得る唯一の方法と、認識される可能性が高かった。







































