リービットは現代では女性天文学者として伝えられていますが、実は当時天文台で雇われていたただのパートタイマーでした。
パソコンもなかった当時、観測した膨大な天体写真を整理するのは大変な作業で、ハーバード天文台では女性パートタイマーを雇ってその整理をさせていました。
リービットはそんなパートタイマーの一人で、毎日大量の天体写真乾板を整理してカタログ化していたのです。そしてその作業を行う中で、彼女はマゼラン雲(銀河だが当時はまだ星雲と考えられていた)の領域に映る星の中に何百日もの時間をかけて明るさが変化している星があることに気づきます。
これ自体はセファイド変光星と呼ばれるもので、別段特別なものではありませんでしたが、彼女は膨大な写真乾板の整理をするなかで、このセファイド変光星をマゼラン雲の中に複数見つけ、それを比較したとき明るさの変わる周期が同じ星は同じ明るさであり、周期が長いほど最大輝度が明るくなることに気づくのです。
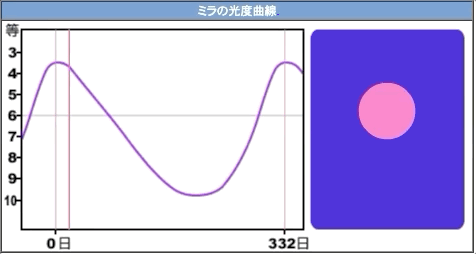
マゼラン雲の領域に見つかったセファイド変光星はだいたい地球から同じ距離にある星と理解することができます。そのためリービットの気づきは、変光周期が同じセファイド変光星は同じ明るさで光っていることを示していました。
宇宙の距離を測るのが難しいのは天体がそれぞれバラバラの明るさで輝いているためです。
もし同じ明るさで光る星を特定できた場合、見える明るさの違いから両者の距離を比較することができます。なぜなら明るさは距離のニ乗に比例して減衰していくからです。

セファイド変光星の輝度と周期の法則を発見したことで、リービットは遥か遠くの天体と地球に比較的近い星(天の川銀河内の星)の距離を比較する方法を世界で初めて示したのです。









































