こうした骨格の変化がありながらも、このマウスたちは深刻な病気や異常を示しませんでした。
通常、GLI3遺伝子が完全に機能を失った場合は指が余計に生えるなど深刻な奇形が起きますが、この小さなアミノ酸変異では、そうした重大な問題は起こりませんでした。
つまり、このネアンデルタール型のGLI3変異は、骨格の成長バランスをわずかに調整しつつも、体全体の健康を損なわない範囲で影響を与えたと言えます。
これは進化の観点からも重要なポイントです。
体の構造に影響を及ぼす遺伝子変異が致命的な問題を引き起こさずに次世代に受け継がれる場合、その変異は長い時間をかけて集団内に定着していく可能性があるからです。
こうした結果を踏まえると、私たち現代人が受け継いだ「古代の遺伝子のかけら」は、私たち自身にも気付かれないほど小さく微妙な変化を与えているのかもしれません。
では、そのような小さな変化は、実際に現代人にもどのような影響を与えているのでしょうか?
現代マウスの骨格が「ネアンデルタール風」に変化した理由
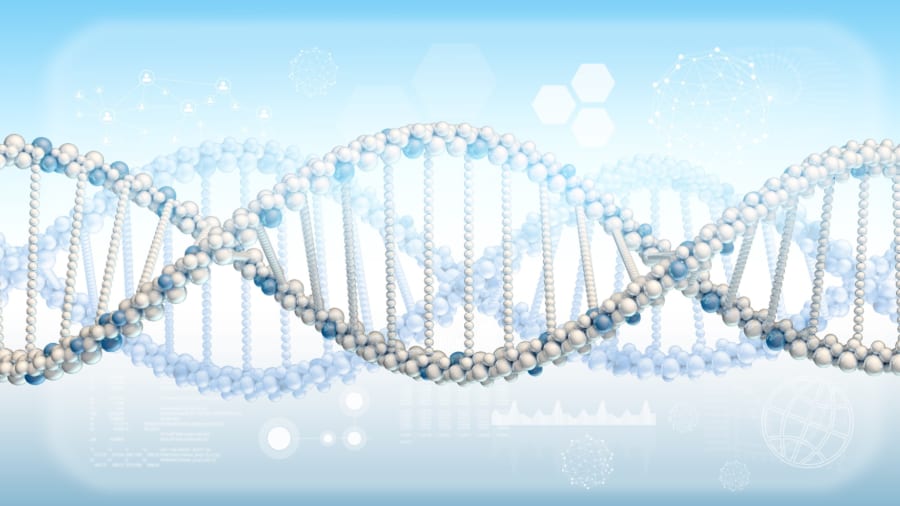
今回の研究は、私たち現代人が今も受け継ぐ「ネアンデルタール人やデニソワ人由来のたった一つの遺伝子変異が、骨格の形にまで影響を与えている可能性」を示しました。
つまり、絶滅して何万年も経つ古代の人類の遺伝子が、現代の私たちの体の中で静かに働き続けているかもしれないのです。
ネアンデルタール人やデニソワ人が持っていたこのGLI3遺伝子の変異(R1537C)は、現在のヨーロッパ系の人々の約4〜7%ほどに見られることが知られています。
アジア系の人々にも数%ほど見られますが、アフリカ系の人々にはほとんど存在しません。
コラム:なぜGLI3変異は多めに人類に引き継がれたのか?
私たち現代人のDNAには、ネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子が平均して約1〜4%ほど含まれています。ところが、今回研究された「GLI3」という遺伝子の変異(R1537C)は、ヨーロッパ系の人々では約4〜7%という比較的高い割合で残っています。これは平均値(約1〜4%)に比べると非常に高い頻度で、なぜこの変異が特に多く現代人に受け継がれているのか疑問に思うかもしれません。論文によると、このGLI3の特定の変異(R1537C)はネアンデルタール人やデニソワ人といった絶滅した古代の人類に共通して見られるもので、進化の過程で比較的無害だったことが重要だった可能性があると推測されています。





































