さらに興味深いことに、薬物治療を受けている患者グループ内で、「冒険的衝動性」と脳構造との間に明確な関連が見つかりました。
具体的には、冒険的衝動性のスコアが高い患者ほど、「右中帯状回」(感情や意思決定に関わる領域)の灰白質体積が大きくなる一方、「右後頭葉上回」(視覚情報の処理に重要な領域)の灰白質体積は小さくなるという相反する関係があったのです。
これは、「冒険好きでリスクを取るタイプ」のADHD患者が特定の脳構造を持っている可能性を示しています。
この発見は、薬物治療によって複雑化していた脳表面構造の話とはまったく別のもので、ADHD患者の行動特性が脳内のどの部位と関係しているかを探る手がかりになるかもしれません。
こうして整理すると、今回の研究では、薬物治療によって脳表面構造が明らかに複雑化する一方で、灰白質の体積や症状そのものはあまり変化しないこと、そして「冒険的衝動性」という行動特性が脳の別の部位と関係している可能性を示すという、ふたつの興味深い発見が得られたことがわかります。
では、これらの意外で複雑な研究結果を踏まえて、私たちは今後、ADHDの治療やサポートについてどのように考えていくべきなのでしょうか?
ADHD治療薬がもたらす「脳の変化」の真の意味は?
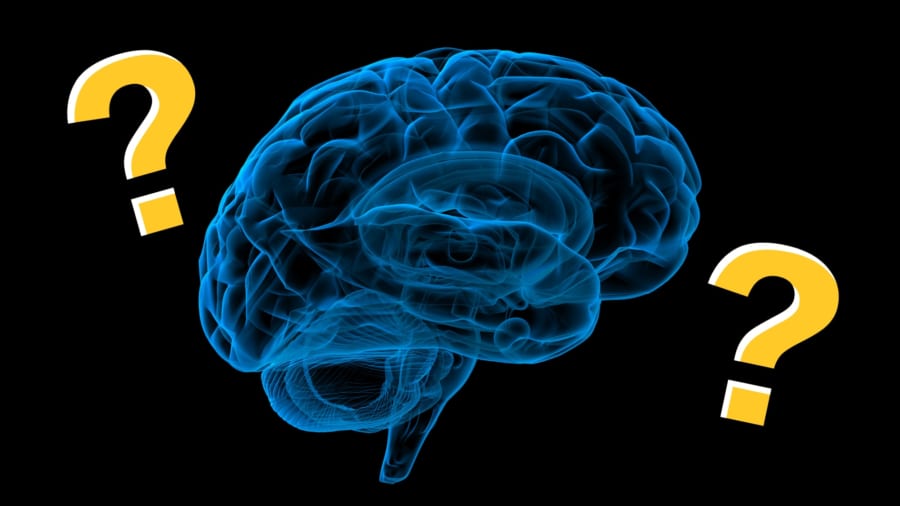
今回の研究によって、大人のADHD患者が精神刺激薬を長期間服用すると、脳表面のシワや谷が複雑になるという興味深い変化が示されました。
研究者たちは、ADHDの治療に使われる精神刺激薬によって脳の表面が複雑になる現象について、その変化が脳の発達や成熟を促している可能性を考えています。
脳の表面のシワが増えたり、谷が深くなったりすることは、一般的に脳が成熟していることや認知機能が向上していることを示していると考えられているからです。
特に眼窩前頭皮質と呼ばれる脳の部位は、感情をコントロールしたり、何かを決定するときの判断力や報酬を感じる仕組みに重要な役割を持っています。したがって、この部分の複雑さが増すことで、感情の調整や意思決定の力が向上する可能性があると推測されています。










































