さて、この時期の10年間、私は日本全国で社会調査に明け暮れていた。
まず「少子化」をテーマにした3年間の自らの「科学研究費」申請が通っていた。さらに政府からの補助金をうけたシンクタンク「日本健康開発財団」からの共同研究の責任者を引き受けてもいた。加えて、ニッセイ財団の補助をうけて富良野市におけるNTTのLモード電話機を使った地域福祉実験も手掛けていた。そして、長く付き合ってきた長寿社会開発センターの共同研究者も担っていた。
4種類の社会調査結果を1冊にまとめた
せっかく貴重な研究費補助を受けたのだから、しっかり調査して、その成果を報告書に止まらず、単行本にまとめておきたいという気持ちから、8年間に及ぶ4通りの調査結果をテーマごとに精査して論文に書き直し、『社会調査から見た少子高齢社会』として刊行した。
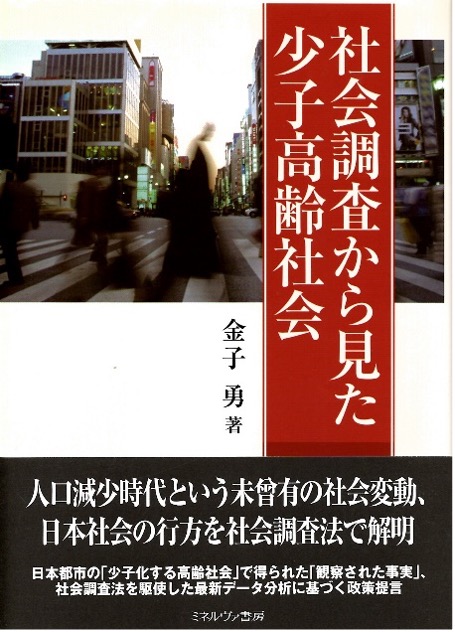
実際のところは、表1にまとめた「論文の書き方」を使いながら、私自身で4通りの社会調査結果を分析して単行本にまとめたことになる。
ただこの時期になると、北大大学院文学研究科社会学専攻修士課程と博士課程で指導した若手の研究者が育ち始めていたので、かなりな業務分担をお願いできるようになっていた。
二人の若手研究者
一人は都市コミュニティと高齢化研究を専門とする松宮朝氏(現・愛知県立大学教授)であり、修士課程からずっと指導教授を引き受けていた。調査の当時は博士課程在学から助手であったが、いろいろな手伝いをしていただき、報告書では共著論文執筆もお願いできた。
もう一人は青山泰子氏(現・自治医科大学准教授)であり、医療社会学・高齢化研究を専門として、社会調査にも熱心であった。松宮氏と同じく博士課程在学から助手の時代であったが、学生引率などにも細かな配慮を忘れない若手研究者であった。この二人の活躍にどれほど救われたか分からない。両氏ともに私が博士(文学)の学位認定の主査を務めた。








































