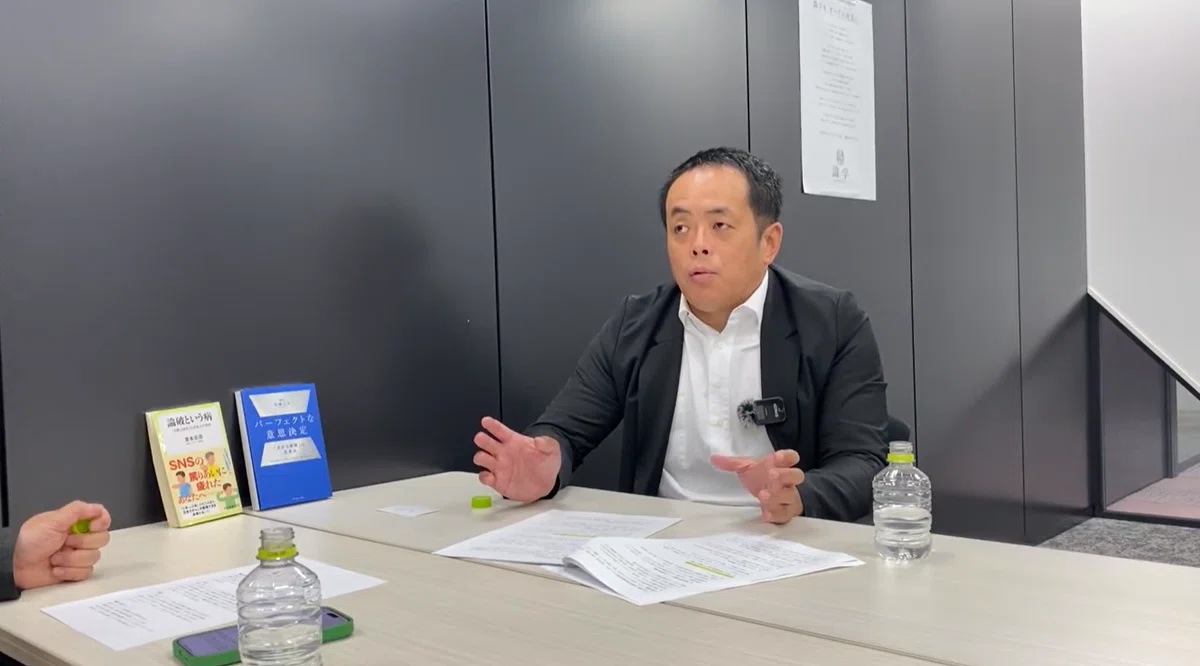
倉本:なんかその、従業員に理解してもらうやり方は、識学さん的な方式もあれば、もうちょっとソフトタッチな方式もあるかなと思うんですけど、その究極的に目指す部分として、その会社の現状を 分かってもらう・分からせることをしないと、その下からの提案が、めっちゃズレたものしか出てこないんで、結果として 無視せざるを得ないみたいな感じになって、お互い「分かってねえ」みたいな感じになるなと思ってて・・・
例えばIT企業の若い人とかが、なんかうちもGoogleマップみたいなんやりましょうよみたいなこと言って、いやうちにできるわけないじゃん、みたいな。
なんかこういうこと頻発してるなと思ってて、そうじゃなくて今のその会社の規模感とか資金力とか自分たちのアセットみたいなことを考えると、こういうことならできるよねっていう方向性が示されていれば、それに応じて噛み合った提案が上げられるようにもなるなと思っているんですが・・・
2. ケーキを切って配布するように「責任」を丁寧に配る経営が必要
安藤社長:それはですね、勿論あると思いますが、ただ経営人が見ている景色と、従業員に見えてる景色って全く違うんで、僕らが話す前提条件を例えば2年目社員に聞かせた時に、そのことをやっぱり理解できないんで・・・
倉本:ちゃんとケーキを切り分けて配布するようなことをしないと・・・
安藤社長:そうです。配布して、「この中で」あなたの頭を使って全力で考えてくれ、ということを言っていくことが大事ですね。といっても「ちょっとはみ出る」ぐらいの提案ならズレようがないんですけど、要は「本来経営者が考えないといけないようなところ」を、従業員に考えさせようとすると絶対ズレます。
僕もふりかえって、NTTドコモの新入社員時代に生意気でしたんで、ドコモの上層部はわかってない、みたいな感じで経営陣のところに時間貰って言いに行ったりしてたんですけど、今考えるとめちゃくちゃ恥ずかしいです。












































