では以下、テキスト版の前編記事をお読みください。
1. 「ちゃんとした組織の規律」があるほうが、「社員の意見」を取り上げることができる
安藤社長:みなさんこんにちは、識学チャンネルということで、今日は経営コンサルタントで思想家の倉本圭造さんにお越しいただいてます。
倉本:よろしくお願いします。僕は中小企業コンサルタントをしながら、同時に「思想家」業として、色々と社会問題に対する提言とかをしているんですが、片足を「中小企業コンサルティング」の世界に突っ込んでいるものとしては、識学さんのお名前は当然耳にしていたわけですけど・・・
ただ個人的な感じとしては、かなり遠いキャラクターなのかなという部分がありまして、今回お話いただいたことを僕のクライアントとかに言ったら「マジっすか」という反応というか、かなり違う方向性な印象だったんですね。
ただ今回この本とかを読ませてもらうと、結構僕の言ってることと近い部分もあるし、「宗教だとか軍隊だとか根性論じゃないか」的な、ネットでよく見る識学さんのイメージとは随分違う面もあるな、と思いまして。
2週間前このお話をいただく前の僕の印象と、実際に本読んでみると印象変わったなという部分を比べていくと、世間における識学に対する印象の誤解が解ける部分もあると思いますし、今の日本に何が必要なのかという話もできればいいなと思っています。
安藤社長:そうですね、そういう話もぜひしていきたいと思います。僕も著書の方とか読ませてもらって、わりと本当に似ている部分もあるなと思いました。
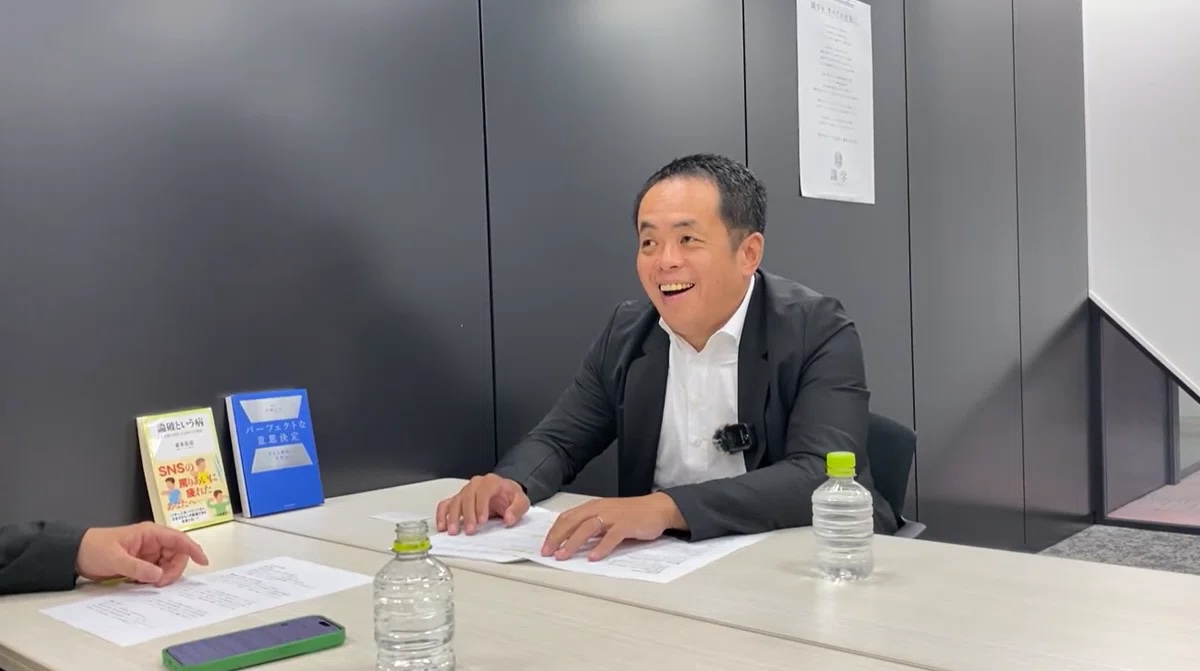
倉本:特に思ったんですが、「従業員から情報を吸い上げる・社員の意見をちゃんと取り入れる・・・ためには組織の規律がむしろ必要」っていう話なんですよね。
僕のクライアントは、僕のキャラを反映して、識学さんではあまり推奨されてないワンオンワンだとか、従業員アンケートだとかをやってる企業も多いんですが、そういう経営者を見てると、案外自分の立場をキチンと守って規律が崩壊しないようにする小ネタを色々持ってるなと思っていて、要するに「規律がちゃんとあることで情報を吸い上げることも可能になってる」みたいなところがあるなと思ってるんですね。









































