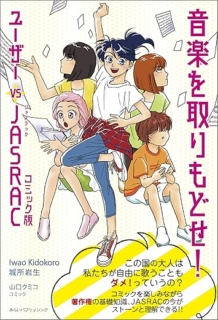松本:いくら著作権的にOKでも全然リスペクトないということになると批判も浴びるし、売れることもない。
小沢:イスラエル軍を美化するような投稿(下図)については、一ジブリファンとしては嫌だなと思いますね。
松本:この議論というのは、割と著作権の話に重点が置かれすぎているが、著作権的にOKであれば何やってもよいかというと決してそうではなくて、むしろ、人間は感情の生き物なので、ちゃんとリスペクトありますかというところこそ問われるべきかなと思う。
小沢氏はこの後、生成AIの利用で権利侵害をしないための各種ガイドラインとして、文化庁の「AIと著作権Ⅱ」および経済産業省の「コンテンツ制作のための 生成 AI 利活用ガイドブック」を紹介、いずれも具体的な事例が多くわかりやすいので、一読を勧めた。
RIETE講演に戻って、プレゼンの結び「今後の展望」を以下に要約する。
アシスタント、スクリーントーン、コピー機、3DCG、デジタル作画、これらは出た当初ずるいと言われたが、今ではもう当たり前に使われている。ワープロを最初に使った小説家 安倍公房氏は、そんなものでは魂がこもらないとの批判に対し、「馬鹿な。万年筆から出てくる『魂』なんて、ずいぶん軽薄な『魂』もあったもんだよ」と反論した。
AIの時代に創作で最後に残るものは、選択と責任だと思う。漫画家はアシスタントが描いた背景も自分の作品として世に出し、それに対するネガティブな評価も受け止めている。選択して、選び取る責任という基本的な構造は、アナログの時代から何も変わっていない。
漫画家は究極において、漫画だけ描いていたいので、AIは漫画を描く以外の雑務をサポートするツールになってもらいたい。
この後に続く、RIETI講演のコメンテイターによるコメントとQ&Aについては②で紹介する。
■