このような講義のプリントを基にして、ワープロを使って少しずつ各章の論文として清書し始めたのが、1992年の正月からであり、その年の秋の終りにはすべてを脱稿していた。
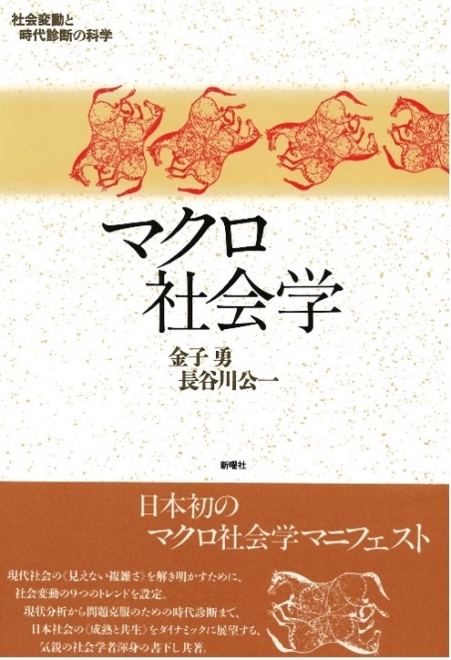
6年がかりで刊行
そして共著として刊行されたのが1993年の3月であった。4月からの1年生向けの講義では、本書を使って15回の「マクロ社会学」を講義した。
多くの場合、「マクロ社会学とミクロ社会学の区別」と「ゼーション現象と社会変動の研究」から始めて、「産業化と都市化」で3回、「情報化と国際化」で4回、「高齢化と福祉化」で3回、そして3回の「社会調査の方法」でまとめた。本書を使うようになってから、北大での受講生は毎年500~700人に増えたので、期末試験の採点では1週間かけて答案を読んでいた。
そのうちに『社会学評論』では富永教授の「書評」が出て、それ以降も専門誌で橋爪大三郎や三重野卓などかなり多くの専門家に「書評」していただけた。そのためか本書は毎年増刷が続き、2004年4月の8刷まで部数が伸びた。専門書では破格の部数が出たことになり、新曜社の社長も編集者の小田氏も喜ばれた。
Amazonでの書評
まだAmazonなどが無い時代であったが、刊行して20年後の2014年3月に投稿されたあみとさんの「書評」では、
「第1章 マクロ社会学の現在」と「第11章 社会調査の方法」は勉強になった。前者は84年の『社会学評論』でパーソンズの構造-機能主義への理論的懐疑が提出されて萎縮していたマクロ社会学の可能性を示している。後者は理論社会学が何をめざすべきかを示している。構造主義以後の理論社会学が微分幾何学ベースとなった現実を考えればこの本の持つ意味は大きい。すでに本書が出版されて20年が経つが日本固有の社会学史には欠かせぬ一書となろう。良書である。
と評価されている。この「書評」にも感動した。
このように生命の長い共著が出せたのも、二人の出会いを取り持たれ、執筆の際にも適切なコメントをたくさん寄せられた編集部の小田氏のご尽力の賜物であり、ここにも縁と運が大きく作用している。






































