後に述べる手形との一番の差異は、小切手の場合、支払うお金が既に存在するということ、つまり信用という要素がどこにも存在しないということである。
銀行の存在を前提にするなら、そのお金は前もって・・・・前もってAが銀行に預金しているのである。小切手を使うことによって、Aはわざわざ預金を下ろしに行かなくて済むし、Bは受け取ったお金を持ち歩くリスクから解放される。もちろん有価証券である小切手を紛失するリスクはあるが、現金の紛失と違って救済措置がある(横線小切手、線引小切手などイギリス人の考えた工夫)。
小切手は、決済手段として使用されるが、それが必要となる一般的なケースは商品の売買であるから、小切手の歴史は(手形も同様)資本主義より古い。
「小切手は14世紀のイアリアで発生し、オランダを経て、17世紀のイギリスで発展を遂げた」(大塚龍児他『商法Ⅲ-手形・小切手 第4版』、P.30、2011年、有斐閣)
小切手は支払いの源となるお金が同時的に存在する。現代では、存在場所は銀行の当座預金である。
原則無利子という当座預金は、利子が当たり前の銀行界では、むしろ不思議な制度なのだが、実はそれがすべての銀行業の基礎にある。このあたりの説明は自著『金融の原理』に書いた。
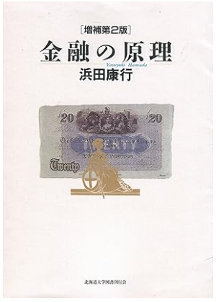
小切手は、現状では銀行を介する電子決済でほぼ完全に代行されている。その特徴はon demand(要求払い)であり、ノータイムの電子決済とよく附合する。
紙の存在の小切手は事実上なく、やがてその概念も消滅するだろう。後の人々は、昔のことが書いてある商法の本か歴史書でしか、それを知ることはできないだろう。紙の小切手は紙の電話帳と同じように博物館に陳列されるかもしれない。
手形
手形も商業取引とともに発生し、資本主義とともに発展するが、その機能は小切手とは異なっている。その原理的な説明は『The NEXT』でも要約している。
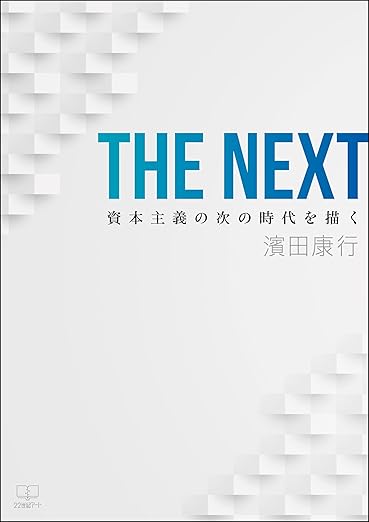
小切手との違いは、手形がその発生時から必然的に信用期間を含むことだ。小切手は要求払い(on demand)である。先の例でいえば、Aは受け取った小切手をすぐに銀行に持ち込んで現金化できるし、自分の預金に加えることもできる。現実には、多少の時間はかかるが理論的には一覧払いに時間はない。




































