1897年に遠洋漁業奨励法を公布して外国船団に対抗し、日本の海獣猟業は急速に発達しました。ラッコやオットセイを獲りまくったわけです。
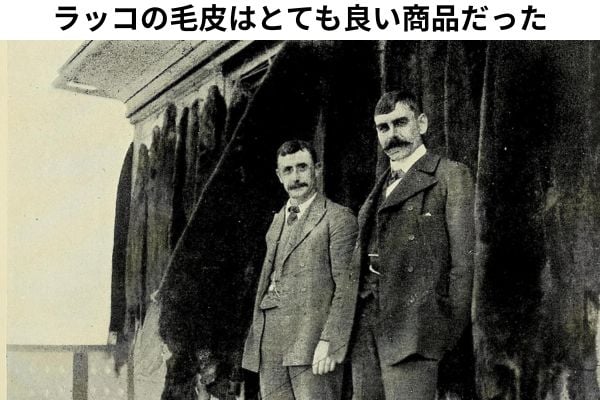
1897年頃、外国船団は日本沿岸に姿を見せなくなりました。
要するに毛皮のために乱獲され、絶滅の危機に瀕したのです。乱獲されて絶滅した生物は、「簡単に獲れる」「美味しいか毛皮目当て」のことが多いですね。後先考えない人間の欲のせいで消えていくのです。
その後、1911年にアメリカ、ロシア、日本、イギリスの4か国が「北太平洋アザラシ条約」を締結し、ラッコを含めた海獣類の保護を開始しました。
それでも数の回復には時間がかかり、依然として低迷する個体数。そのため、ワシントン条約で保護されるようになりました。
そんな中、1989年に起きたタンカーの座礁事故は悲劇でした。ラッコに原油が付着した結果、体毛が海水で濡れてしまい体温を奪われて凍死、もしくは体毛の間にたっぷりと空気を含ませることができなくなり、浮力が減少して溺死して、1000頭あまりのラッコが死んでしまったのです。
ここまでが、日本の水族館からラッコがいなくなる理由と、そもそもラッコがどうして保護されるに至ったかのあらましです。

ラッコ飼育、もうひとつの問題と新しいアイドルの登場
水族館はもうひとつ、別の問題を抱えていました。
ラッコは北太平洋に棲息するため、飼育するプールの水温は低く保つ必要があるほか、水は清潔でないと適切な体温調節と浮力を得られません。施設の管理に手がかかります。
さらにラッコの餌はウニ、貝、甲殻類といった高級食材。しかも1日に体重の25%の量を食べます。メスで15~30kg程度の体重があるので、仮に体重が20kgだったとしたら毎日5kgの高級食材を平らげているわけです。










































