それぞれの粒子が担う物理法則も異なるため、衝突の結果を示す方程式は通常なら全く別のものになるはずだと考えられてきました。
(※素粒子そのものが物理法則を背負っている例として、光がかかわる物理法則は光子という素粒子によって背負われています。また素粒子の質量にかかわる物理法則はヒッグス粒子、核内の強い力がかかわる物理法則はグルーオンによって背負われています)
ところが最近、スタンフォード大学のランス・ディクソン氏とその共同研究者たちは、まるで関係のないように見えた2つの散乱振幅が驚くほど似通っていることに気づきました。
最初は「そんなはずはない」「計算のバグかもしれない」と疑われたそうですが、コンピュータを使った高精度の再計算でも同じ結果が得られました。
何千、何万という複雑な項を順番に比べても、どこまでも不思議な形の対応が崩れません。
こうして「2種類の違う散乱なのに、計算式の一部が同じ構造をしている」という謎の事実が浮上し、彼らはこの現象を「対蹠双対性」と呼ぶようになったのです。
そして複数の現象が同じようにまとめられてしまう“二重性”が見つかったことで、「私たちの世界が実はもっと単純な構造をしているのではないか」「まだ明らかにされていない深いルールがあるのではないか」という新しい可能性が広がりつつあるのです。
異なる物理法則を重ねる「二重性」
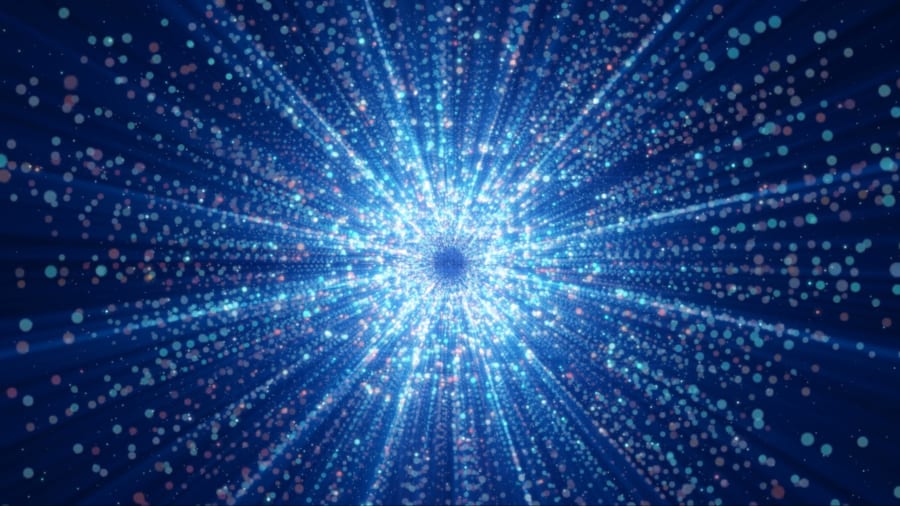
実は、私たちの宇宙を解き明かすためのさまざまな理論の中には、「一見まったく違う仕組みを使っているのに、深いところでは同じ構造に行き着く」という不思議な対応関係がしばしば見つかっています。
これを総称して「二重性(デュアリティ)」と呼びます。
たとえばある理論研究では、重力がある歪んだ空間(AdS)が、重力のない平坦な世界(CFT)を比べてみたとき、普通なら全然別の理論に見えるのに、深いところでは同じ数式で記述できる――という発見がありました。














































