目次
ビジネス
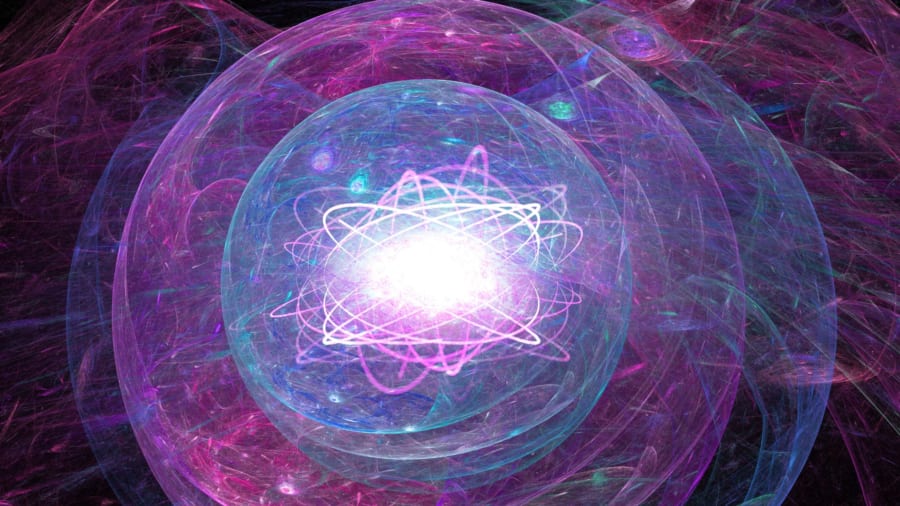
『全然違うはずの物理現象が全て“コピペ”!?』数式が示す不思議な二重性 / Credit:Canva
2025/03/03
光もヒッグスも“同じ式”で語れる?:深いところにある物理現象が共通構造で結ばれている
- 『全然違うはずの物理現象が全て“コピペ”!?』数式が示す不思議な二重性
- 異なる物理法則を重ねる「二重性」
- もっと深いところにある共通構造とは何か?
- 科学哲学的にどう解釈したらいいのか?
『全然違うはずの物理現象が全て“コピペ”!?』数式が示す不思議な二重性
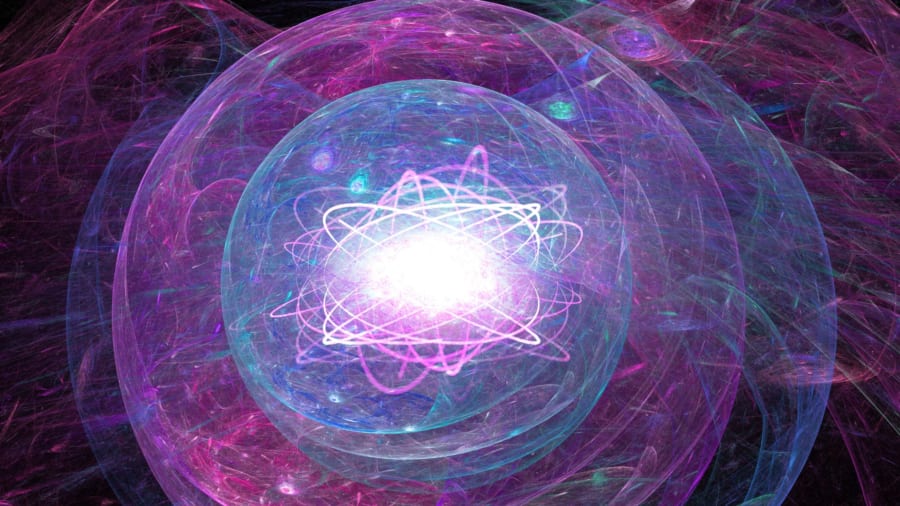
素粒子物理学では、ある粒子とある粒子が衝突した結果「どのような粒子が何個生まれるのか」を調べ、その確率を数式として表すことを「散乱振幅」と呼びます。
イメージとしては、2つの玉がぶつかったときに、どんなふうに砕け散ってどんな破片が飛び出すか――その可能性を全部足し合わせるような計算だと思ってください。
この散乱振幅は、粒子の種類や力の伝わり方によって計算方法が変わり、通常は「これはこの力がはたらくからこの組み合わせ」「あちらは別の力がはたらくから、まったく違う組み合わせ」となるはずです。
たとえば「2つのグルーオン粒子を衝突させて4つのグルーオンを生成する過程」と、「2つのグルーオンが衝突してヒッグス粒子1つとグルーオン1つを生み出す過程」は、登場する素粒子が異なるため物理現象的には別物と考えられていました。
本来なら、現象を示す方程式もかなり違う形になると思われていたのです。
ちなみにグルーオンは原子核をつなぎとめる強い力の媒体であり、ヒッグス粒子は質量の起源に関係する粒子として知られています。
この2つの衝突は、「バスケボールとテニスボール」「野球ボールとピンボール」をぶつける違いとは本質的に異なります。
ボールたちはどちらも多数の粒子から構成されており、古典物理で説明できる範疇の運動をしているからです。
しかし素粒子同士の衝突は、日常的な「ボールとボールがぶつかる」話とはまったく違うレベルの現象です。
グルーオンやヒッグス粒子のような基本粒子は、その内部構造をさらに分解できない存在と考えられています。












































