このフェスティンガーの実験は、「人は自分の行動と信念が矛盾すると、無意識のうちに信念を変えて自分の行動を合理化しようとする」という認知的不協和の基本原理を示しています。
報酬が少ない場合、不協和を減らすために態度を変える(「作業は楽しかった」と思い込む)。報酬が多い場合、「お金のためにやった」と認識し、態度は変えない。
認知的不協和が生じると、人の心は強いストレス状態に陥ります。そのため人は心の健康を守るため、無意識にこの状態を解消しようと認知を歪めるのです。
では、このような認知的不協和の基本原理は、私たちの周りで見られる行動をどのように説明しているでしょうか。
人々はどのように自分を正当化するのか
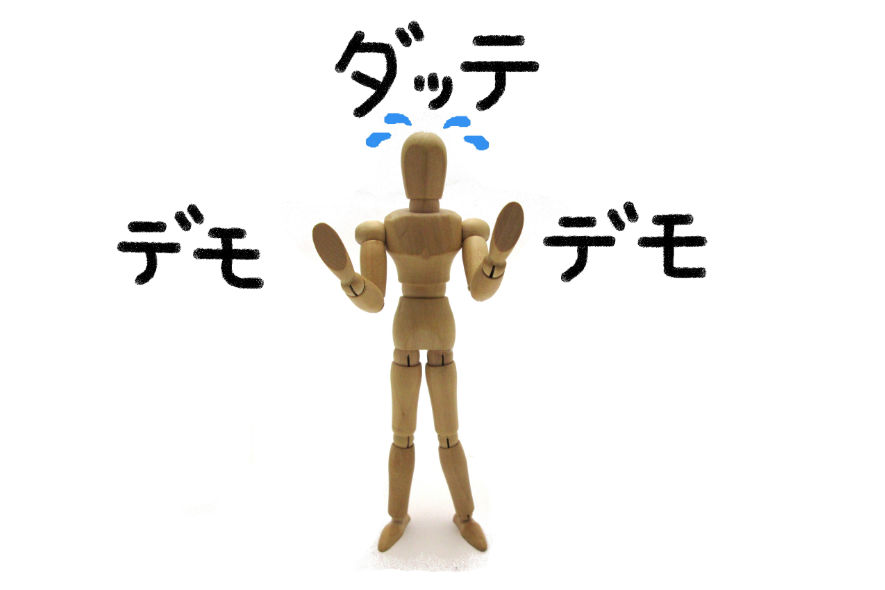
私たちの身の回りでも、フェスティンガーの実験で示されたような認知的不協和の基本原理が見られます。
最初に示していた例から考えると、喫煙者の場合、「タバコを吸いたい」という欲求に対して、「肺がんになりやすい」という情報は認知的不協和を起こします。
そこで喫煙者は「タバコは肺がんになりやすい」という認知を歪め、「そんな事実はない」「我慢する方が身体に悪い」と考えることで気持ちよくタバコを吸えるようにします。
また、「タバコが肺がんを誘引する」のではなく、「肺がんになりやすい人がタバコに引き寄せられているだけ」と、タバコと肺がんの因果関係を否定するかもしれません。
「なるべく節約したい」のに「ガチャ課金したい」人の場合も同様で、「課金は無意味な支出」と考えると、せっかく楽しみでゲームを遊んでいるのにストレスが強くなってしまいます。
そこで、「節約ばかりしていたら心の方が貧しくなる。課金は食費と同じ必要な出費だ」「いいゲームだったから楽しませてもらった分のお礼をしているんだ」と認知の仕方を変えることで、行動のストレスを減らすのです。














































