日弁連ガイドラインでも述べているように、第三者委員会は「不祥事によって失墜してしまった社会的信頼を回復すること」を目的とし、「企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するために設置」されるものである。
私は、企業の外部者の専門家だけで組成する「第三者委員会」の草分けとなった不二家消費期限切れ原料使用問題での「信頼回復対策会議」の議長を務めたほか、多くの企業等での第三者委員会委員長を務めてきた(【第三者委員会は企業を変えられるか 九州電力やらせメール問題の深層】毎日新聞社:2012)。
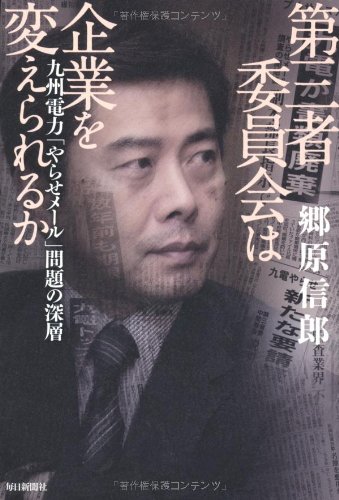
そして2016年から2020年に日経bizgAteに掲載された《郷原弁護士のコンプライアンス指南塾》では、【企業の不祥事対応における第三者委員会の活用】を3回にわたって連載した。
その連載の冒頭で、
昨年来、日産自動車、スバルの完成検査をめぐる問題、神戸製鋼所をめぐる問題を発端とする品質データ改ざん問題、スルガ銀行のシェアハウス融資をめぐる問題など、企業不祥事が相次いで表面化している。不祥事の事実関係の調査・原因究明、再発防止策の策定を求められる不祥事企業にとって、内部調査で対応するのか、外部弁護士を含めた調査を行うのか、第三者委員会を設置するのかは難しい判断である。また、委員会を設置する場合に、委員長・委員をどのように選任するのか、調査体制をどう構築するのかが重要となる。
と述べている。
一般的な企業不祥事では、問題となる事実の中身は明確であり、そのような問題について企業側が認めて謝罪した上で、その問題事実の詳細を明らかにし原因分析等の調査を行うために第三者委員会が設置される。
フジテレビの問題は、それとは異なる。週刊文春の報道を発端に疑惑が発生し、それに対するフジテレビ側の対応が批判の対象とされ、会長・社長が引責辞任に追い込まれるという「重大不祥事」に発展した。




































