哲学を専攻すると本当に「頭が良くなる」のでしょうか?
そんな疑問に、アメリカのウェイクフォレスト大学(Wake Forest University)などで行われた研究が答えを出しました。
結果は明快です。
哲学科の学生は、卒業時点で言語力と論理力では全専攻中トップであり、知的な好奇心や多様な視点を受け入れる姿勢といった思考習慣でも上位を占めました。
そして何より重要なのは、入学時の学力の差を考慮に入れてもなお、この「思考力の伸び」が確認された点です。
長年語られてきた「哲学は人を賢くする」という命題が、これまでで最も強力なデータによって後押しされたのです。
哲学にはどんな秘密が隠されていたのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月11日に『Journal of the American Philosophical Association』にて発表されました。
目次
- 哲学はなぜ効くと言われる
- 哲学は人を賢くする?大規模データで検証
- どこまで言える?伸びの意味
哲学はなぜ効くと言われる
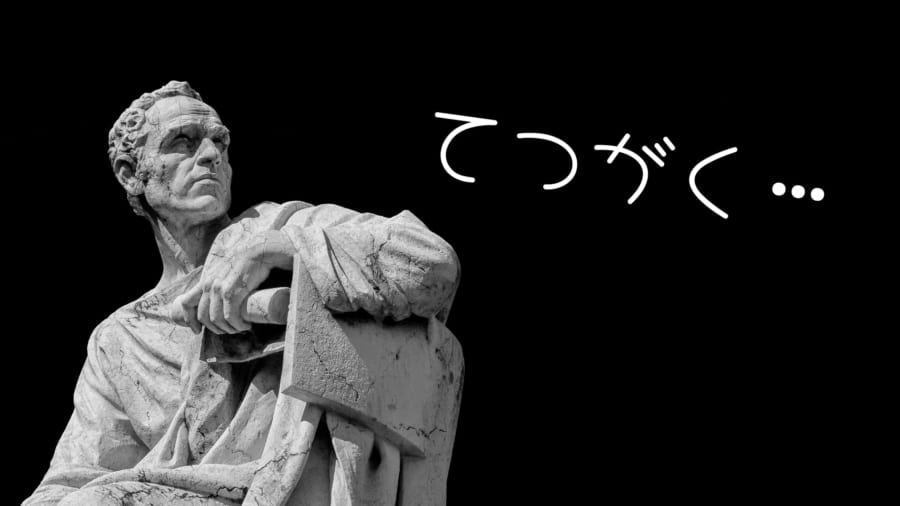
哲学と聞くと、あなたは何をイメージするでしょうか?「難解な話をずっと考え込んでいる学問」と思うかもしれません。
実際そのイメージは、あながち間違っていません。
昔から哲学は、「人間の頭を鍛える」と言われてきました。
なぜでしょう?それは哲学が「言葉」と「論理」を駆使して、物事を深くじっくり考える訓練を行う学問だからです。
こうした訓練を繰り返すうちに、複雑な問題を解きほぐす力や、自分や他人の意見を客観的に検証する力が鍛えられると言われています。
こうした評判を裏付けるデータもあります。
1980年代頃からアメリカでは、哲学を専攻した大学生は、他の専攻よりも大学院入学試験や法律専門大学院試験で高得点を取る傾向があることが報告されています。
ここで登場する試験には、GRE(Graduate Record Examination)とLSAT(Law School Admission Test)の2つがあります。














































