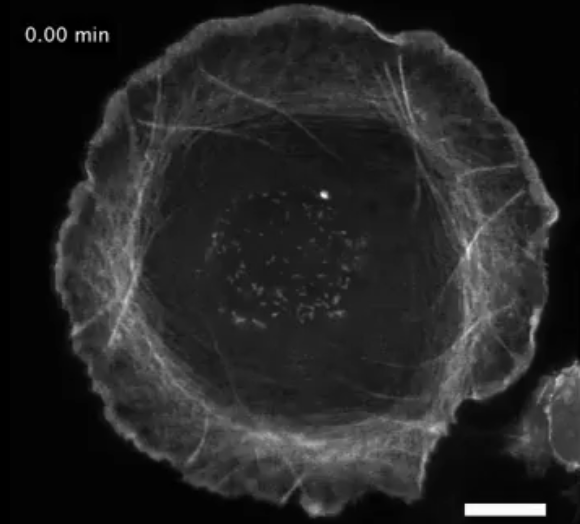イメージとしては、単に水が流れるのではなく、輪ゴムのように自分でグルグルねじれて流れる“渦”が生まれるようなものです。
この理論を細胞の実験結果に合わせてシミュレーションしてみると、なんと、実際の細胞と同じようにアクトミオシンリングの位置――つまり細胞の背中側(上側)にリングがある場合だけ、時計回りの回転が生まれることが分かりました。
さらに、リングが細胞の下側(腹側)にあるように人工的に位置を変えると、細胞の回転は完全に止まってしまう、という予測も立てられました。
この理論の正しさを確かめるため、研究チームは実際に細胞で追加の実験を行いました。
薬を使って、もともと背側(上側)にあったアクトミオシンリングを下側(腹側)へ“引っ越し”させてみたのです。
すると、理論通り、細胞の回転はピタリと止まりました。
つまり、細胞が右回りに回転するためには、“同心円状のアクトミオシンリングが背側にあること”が絶対に必要だと証明されたのです。
ここで注目すべきは、アクトミオシンリング自体は「非キラル構造」、つまり見た目には左右対称で、一方向への“クセ”を持っていません。
それなのに、実際の細胞では“時計回り”という一方向だけの動きが生まれる――これは従来の常識を覆す発見でした。
分子レベルのちょっとした「ねじれ」が、細胞全体の大きな“動き”に伝わり、しかもそれが顕微鏡でもはっきり観察できる「現象」として現れるのです。
この一連の研究によって、これまで謎だった「細胞がどうやって自分の“利き手”を決め、左右の違いを作り出しているのか」という問いに、大きな一歩が踏み出されました。
ミクロな分子の“ねじれ”が、細胞スケールの“ダンス”を生み、その積み重ねが生物の体の“左右”という壮大な物語につながっていく――そんな生命の不思議とロマンを感じさせる成果となったのです。
「細胞の利き手」の意外な仕組み