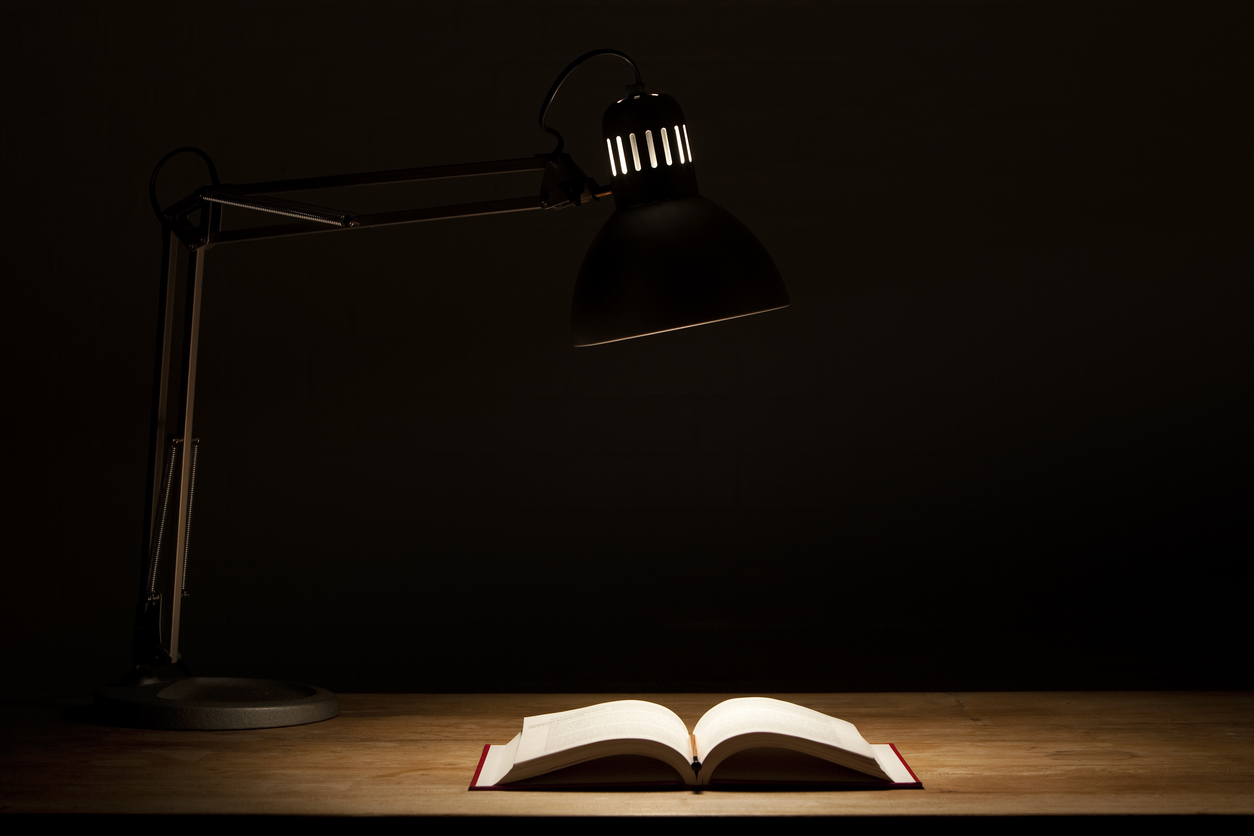
LdF/iStock
現代における戦略研究の「大家」は誰かと尋ねられたら、コリン・グレイ氏(レディング大学)は外せないでしょう。かれは、戦略について、数多くの著書と数えきれないほどの論文やエッセー、記事を書いています。さらに、グレイ氏は学問領域だけにとどまらず、実務でも、レーガン政権の顧問としても活躍しました。かれは戦略の学問と実務の両方に精通した稀有な人材でした。
正直に申し上げると、わたしは、グレイ氏の研究には、あまり興味がありませんでした。もちろん、かれの著作や論文を無視したわけではありません。
「武器があるから戦争は起こる。だから軍縮は平和を促進する」という「俗説」がありますが、わたしはこれに疑問を抱いていました。そこで『武器は戦争を作り出さない(Weapons Don’t Make War)』(カンサス大学出版局、1993年)を手に取ったのです。
ここで主張されている、「政治における政策が戦略を規定するのであり、これにより兵器は意味づけられる」との主張には、半分くらい納得したのですが、その反面、テクノロジーの進歩を反映した戦力という物質的要因が政治的意思決定の選択肢を制約する結果、戦争と平和に大きな影響を与えるのではないかと思ったりもしました。
また、イギリスの古き良き「ヴィクトリア朝」を彷彿とさせるようなグレイ氏の文章や論述には、違和感を覚えずにはいられませんでした。かれの古典的ともいえる研究スタイルは、簡潔性を重んじる論理実証主義の政治学の研究とは、何か相いれないものがあるように読めてしまったのです
『現代の戦略』の意義
そうしたわけで、グレイ氏の記念碑的著作である『現代の戦略』(奥山真司訳、中央公論新社、2015年〔原著1999年〕)は、購入済みだったのですが、ぱらぱらと斜め読みしただけで、本棚に眠っていた状態でした。
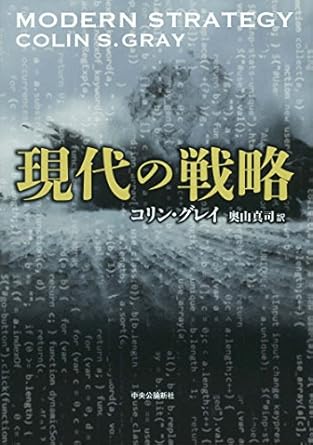
本書は、おそらくエドワード・ルトワック著『戦略論』(武田康裕、塚本勝也訳、2014年〔原著1987年〕)と並ぶ、戦略研究の必読テキストでしょう。そうした基本書を踏まえずして戦略を研究しているというのは無責任だと思い、キチンと読むことにした次第です。













































