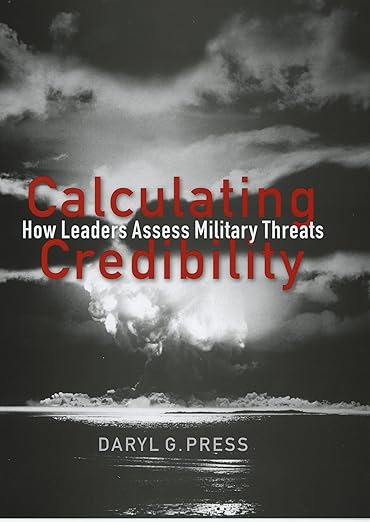
確かに、ヒトラーは英仏の軍事的威嚇を一貫して低く評価していましたが、その理由は、イギリスやフランスが、ドイツのラインラント進駐やオーストリア併合、ズデーテン地方の割譲において、実力で阻止しようとせず妥協を重ねたことから、英仏が弱腰であると判断してつけあがったわけではなく、バランス・オブ・パワーや利益の観点から、両国の脅しの信ぴょう性を判断して行動したということです。
少し長くなりますが、かれの分析を以下に引用してみましょう。
「同盟国(英仏、引用者)の信ぴょう性についてのドイツの議論と行動は、ほとんど常にパワーと利益についてだった…イギリスやフランスの過去の行為やそれが示すところのイギリスとフランスの将来の行動についてではなかった…これらの議論において、ヒトラーは、これまでのイギリスやフランスの優柔不断さの例を指摘することで、かれの侵略的政策を支えることができたはずだが、かれはパワーと利益に議論の焦点を当てたのだ…ズデーテン危機の後でさえ、ヒトラーはイギリスとフランスの信ぴょう性を主にバランス・オブ・パワーに基礎をおいて評価しつづけた。1939年8月14日、ヒトラーは上級軍事顧問に会い、イギリスはポーランドを防衛するために戦うことはないと納得させた…ヒトラーはその理由をこう説明した。『イギリスは、大きくなり過ぎた自身の帝国ゆえに、過剰な重荷を背負っている…フランスは新兵の補充に事欠いており、装備が貧弱で、あまりに多くの植民地の負担がある…フランスとイギリスがとれる軍事的措置は何か。ジークフリート線への突入はあり得ない。ベルギーとオランダを通過する北方への展開は迅速な勝利をもたらさない。このどれもポーランドの助けにはならないだろう…これらすべての要因はイギリスやフランスが戦争を開始することへの反駁なのである』」。
(同書、69-71ページ)
ヒトラーは、ドイツ参謀本部の上級将校たちとは異なり、イギリスやフランスの軍事力について、一貫して低く評価していました。たとえば、ミュンヘン危機において、ドイツの将軍たちは、ドイツのチェコスロバキアへの侵略がフランスとイギリスの軍事介入を招き、ドイツを敗北へと追い込むことを深く懸念していました。










































