他方、ヒトラーはこうした見方に反対でした。ドイツはチェコスロバキアを一撃で倒して既成事実化することになり、こうした迅速な勝利こそ戦争の拡大を防ぐことになると、かれは考えていました。その後、ナチス・ドイツはチェコスロバキアを征服して、シュコダの兵器工場を接収しました。これによりドイツは当時のヨーロッパにおける最大の兵器工場を手に入れて、大量の武器の生産が可能になりました。
このことはドイツの国力を飛躍的に向上させました。こうしたバランス・オブ・パワーの楽観的な計算こそが、ヒトラーを大胆な冒険的拡張行動に走らせたのです。
要するに、侵略を抑止するための威嚇の信ぴょう性は、相手国が過去に対決姿勢で臨んできたのか弱腰だったのかといった行動に対する評価ではなく、バランス・オブ・パワーの認識に左右されるということです。
ヒトラーを大胆にしたパワー
ヒトラーの「虫けら」発言は、どのように解釈すればよいのでしょうか。歴史資料は複数の解釈ができるために、「動かぬ証拠」として扱うことは難しいものです。
これはヒトラーがイギリスやフランスの指導者を見下していた証拠になるのかもしれませんが、プレス氏は、これは、かれの主張の中のささいな一部分であるとみなしています。ヒトラーの「虫けら」発言は、ソ連の意図と行動を分析する議論の間に挟まれた、1つの文章に過ぎないということです(同書、73-74ページ)。
他方、国際関係研究の重鎮であるアレキサンダー・ジョージ氏とドイツ政治外交史の第一人者であったゴードン・クレイグ氏は、『軍事力と現代外交』(有斐閣、1997年)において、イギリスやフランスの宥和政策がヒトラーを大胆にしたことを示唆しながら、「虫けら」発言に触れています(『軍事力と現代外交』84-85ページ)。
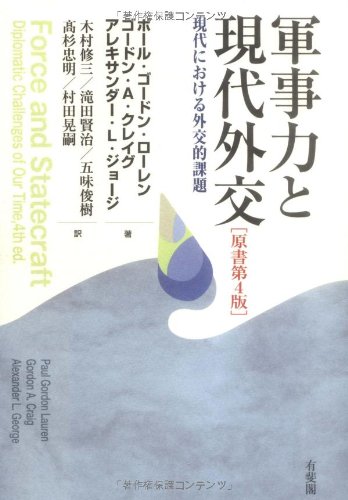
確かに、イギリスとフランスの宥和的姿勢が、ヒトラーの行動に全く影響しなかったとは言えないでしょうが、因果効果の相対的な重みをつけるとすれば、バランス・オブ・パワーに分があるように、わたしは思います。










































