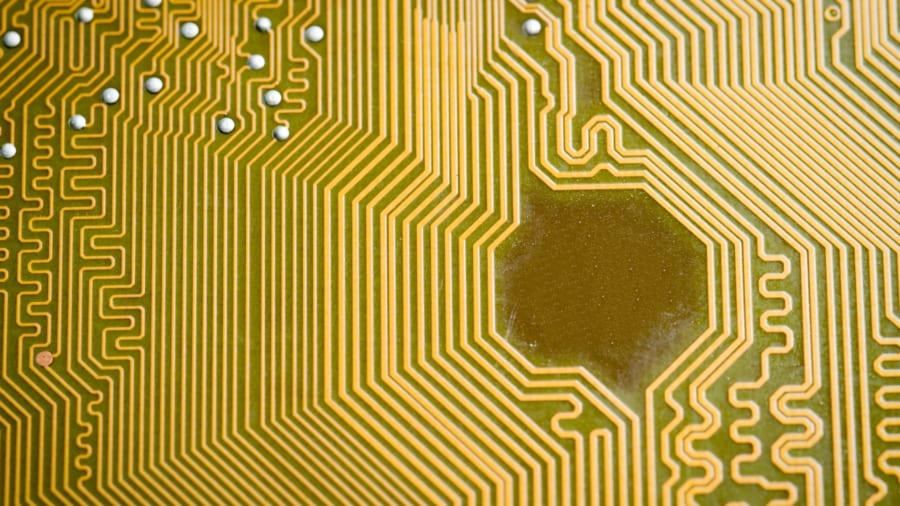しかし、「なぜ微生物は電気を通せるのか?」という疑問が残りました。
そこで研究チームは、微生物が電気を通す仕組みを詳しく調べることにしました。
まず考えられたのは、微生物が金属のような単純な導線の仕組みで電子を運んでいる可能性でした。
もし金属のような単純な仕組みであれば、電気を流すとき電圧を高くすると、それに比例して電流も高くなるはずです。
しかし実際に微生物でテストしてみると、電流は単純に電圧に比例して増えるわけではありませんでした。
代わりに、特定の電圧のところで、はっきりとした「山」のようなピークが現れました。
この「ピーク」の意味は何でしょう?
これは微生物が、特定の電圧付近でしか電子を受け取ったり渡したりできないことを示しています。
例えるなら、電子を手渡しするリレーが微生物の中で行われているようなもので、自由に電子が通れる金属の導線とは違っていたのです。
さらに詳しく調べると、このピークの性質は「マルチヘムc型シトクロム」というタンパク質の特徴とよく似ていることがわかりました。
このタンパク質は、細胞内外で電子を受け取ったり渡したりする役割を持つことが知られています。
つまり微生物は、細胞の中にタンパク質でできた電子リレー(バケツリレーのような仕組み)を持っている可能性が示唆されたのです。
ですが決定的となったのは、電子が実際に微生物から微生物へ移動していることを直接確かめる実験でした。
実験では、微生物の塊の片側の端から電子を送り込み、反対側の端でその電子が出てくるかを調べました。
すると、片方の端で送り込んだ電子信号が、微生物の細胞間を通ってもう片方の端まで届いていることが確認されました。
その距離は数マイクロメートルで、これは古細菌と硫酸還元菌が細胞間で電子をやり取りするのに十分な距離です。
この結果は非常に重要です。
研究チームは、これがメタン分解を担う微生物たちの共生を支える重要な手がかりとなり、これまで仮説にとどまっていた『細胞間の電子輸送(レドックス伝導)』を実際の測定で示した成果だと考えています。
電子リレー発見の意義と今後の課題