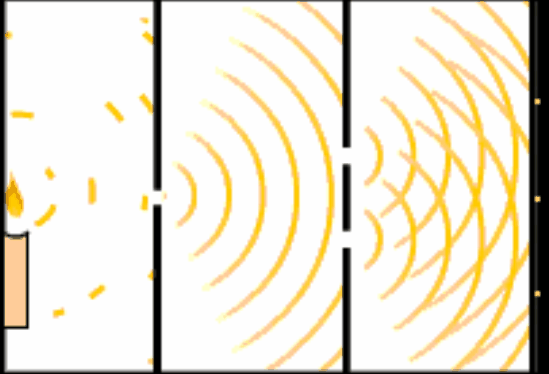アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)で行われた研究により、有名な「二重スリット実験」の「本質」を極限までシンプルにすると、物質の“もやもや”した存在確率、つまり量子の特徴そのものだけで成り立つことが、今回の最新研究ではっきり示されました。
この実験では、通常のように板に空いた二つの穴(スリット)を使うのではなく、代わりに“ぼんやりした位置”に存在する原子そのものをスリットとして使いました。
原子の位置は完全には決まっておらず、「このあたりにいる確率が高い」という、いわゆる“波束(はそく)”という形で広がっています。
そんな原子のそばに1個の光子を飛ばすと、光子は原子のどこかをかすめて通ります。
その際、光子が原子にほんのわずかな影響を与えることで、「どちらを通ったか」という情報がこの世界のどこかに記録されてしまいます。
するとその瞬間、光は“波”としてのふるまいをやめ、“粒”として観測されるのです。
この極限までシンプルにした「原子×光子」の実験でも、「情報の記録が現実を変える」という量子のルールがそのまま働いていることが確認されました。
つまり、重たい観察装置や大がかりなスリット板がなくても、たった一つの原子と光子だけで、量子力学が示す「観察=情報の記録が現実に影響する」ことが実証されたのです。
(※論文の厳密な解説のみが読みたいというひとは最終ページに飛んで下さい)
研究内容の詳細は2025年7月22日に『Physical Review Letters』にて発表されました。
目次
- アインシュタインが残した二重スリット実験の宿題
- スリットの代りを「1個の原子」に任せる究極の簡素化
- 二重スリット実験で「アインシュタインの宿題」を解決した
- ややくわしい解説
アインシュタインが残した二重スリット実験の宿題