しかし『環境問題の知識社会学』(2012)をまとめるに際して、環境系の資料を読んだなかで、3~5月に中国大陸からやってくる黄砂を礼賛したエッセイには驚いた。それは丸善が出している国立天文台編『第84冊 理科年表2011』(2010)の「序」に掲載されていた。
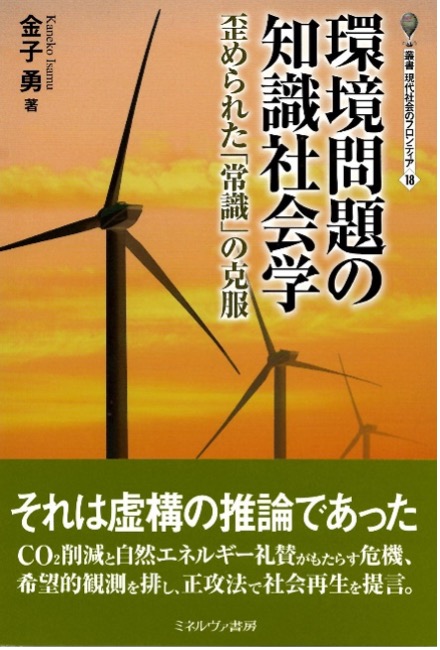
社会学では黄砂は厄介者
社会学では、黄砂が洗濯物を汚し、車のフロントガラスに付着し傷つけたり、視界悪化のために航空機の運航を妨げ、目やのどの障害の原因になり、呼吸器・アレルギー疾患という健康被害をひき起こし、黄砂飛来による光化学オキシダントによるスモッグを発生させるなどのマイナス要因として取り上げることが普通であった。
このように私も含めて、中国からの黄砂はいずれも日本人の日常的なライフスタイルのどこかに負の影響を与えるとの共通理解をしてきた。
環境論では微量元素が富栄養源
しかし『理科年表』の「序」では、黄砂粒子に含まれるSi、Ca、Mg、Na、Feなどの微量要素が貧栄養の日本海に落下することにより、植物・動物プランクトンが増え、小魚、大魚、鳥が増える食物連鎖が活発化することが強調されていた。
日常時間と地球時間との対比
すなわち、日常時間における人間の健康被害というマイナス面に対して、地球時間ともいうべき海洋におけるプラス面での悠久な食物連鎖がわざわざ対置されていたからである。
それは時間の流れを無視した対置というべきであり、日常生活面での判断抜きの自然科学特有の表現と考えられる。その意味で、「序」は機能的に不等価な黄砂による現象を等価と断定した専門家の意図が働いている。
この経験から、社会学とは異なり、環境論での論文や資料の扱いには細やかな注意が肝心だと自覚するようになった。
地球寒冷化に関するアメリカCIAレポート
さて、「地球寒冷化」に関するアメリカCIAレポートが刊行され、一般向けにそのインパクトティームが書き直した文庫版『気象の陰謀』(1977=1983)を読んだのは、44歳で『都市高齢社会と地域福祉』(1993)により博士(文学)を取得した後であった。










































