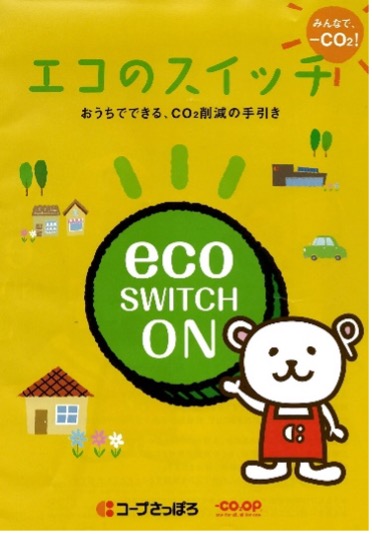
「暮らしの中のエコのスイッチ」
その内容は、暮らしの中のエコのスイッチとして、テレビの主電源を切ると、待機電力消費が無くなり、1時間で5円の節約になり、104gの二酸化炭素削減量になる。パソコンの場合は、1時間で0.6円の節約で、12gの二酸化炭素削減が可能になるというように、「暮らしの中でのエコ」の事例集であった。
圧巻はコープらしく、食料品のカーボンフットプリントが別のパンフとして織り込まれていて、そこにも室蘭工業大学による計算結果が付加されていた(表2)。

表2 コープさっぽろのカーボンフットプリント (出典)金子、2012:126.
食料品のカーボンフットプリント
たとえば表2から、「北海道みそ」500gの製造・輸送・販売に関して、原材料、原材料輸送、工場、製品輸送、店舗ごとに二酸化炭素の排出量が計算されて、最終的には596gの排出量になり、100gのみそを使うならば、119gの二酸化炭素の排出量を前提として、私たちの食卓に並ぶという理解が得られる。
10㎏の「あきたこまち」では、田植えから草刈り、刈り取り、精米、製品輸送、店舗までで7701gの二酸化炭素の排出量になり、100gのご飯では77gの排出量を前提として食べることになる。
2年ほどで中止
この食料品のカーボンフットプリントに象徴的だが、毎日の食卓でもリビングや書斎でも、いちいち二酸化炭素の排出量を考えながら暮らせるものではないから、この試みは貴重ではあったが、2年ほどで終息したように記憶している。
私も含めて客が「エコのスイッチ」をめんどうだと感じたからであろう。その後コープさっぽろからの説明は特になかったようである。
二酸化炭素排出規制では「塵も積もれば山となる」はありえない
いわゆるレジ袋1枚を製造しないならば、二酸化炭素6gの削減になるが、おそらく「塵も積もれば山となる」(Many a little makes a mickle.)にはなり得ない。なぜなら、実際のところレジ袋の追放には成功したが、通常のジェット旅客機は1分間に二酸化炭素排出は600㎏、10分間で6t、100分間では60tにもなることは放置されてきたからである。










































