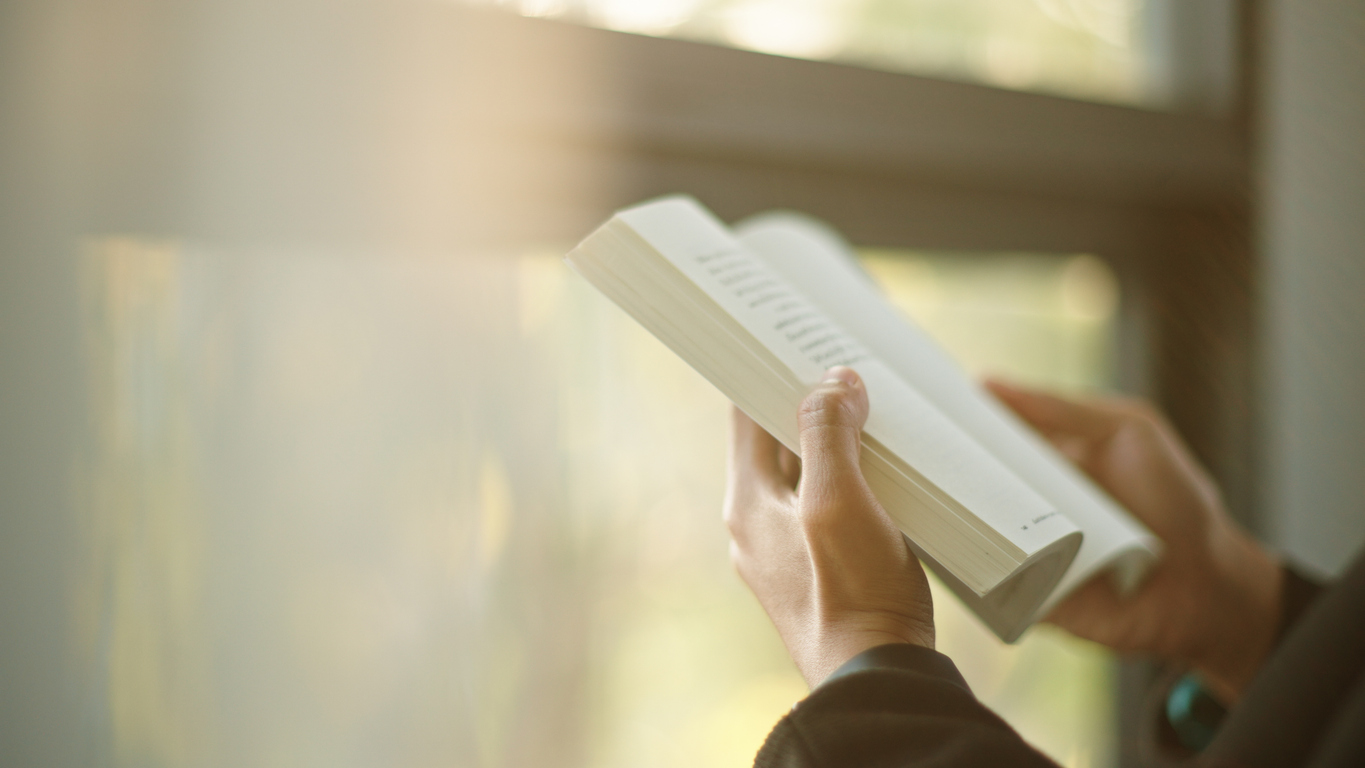
pocketlight/iStock
毎年、7月~8月には太平洋戦争関係の書籍、特に新書が多数刊行される。今年は戦後八十年の節目の年なので、例年以上に刊行が活発であるが、残念ながら内容面、質で評価すると、必ずしも豊作とは言い難い。
ここ10年で太平洋戦争ものの最大のヒットは、吉田裕『日本軍兵士 アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書、2017年)だろう。
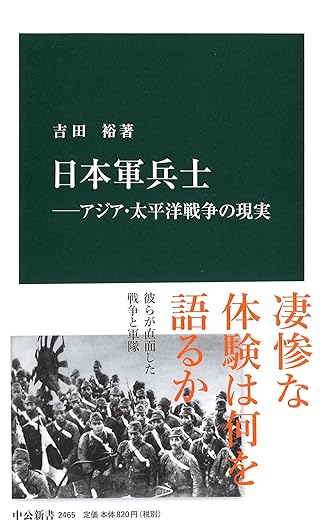
太平洋戦争における日本軍の愚行・蛮行を記した書籍は数知れないが、それらは基本的に軍中央や司令官など上層部の戦略・作戦の拙劣さを批判するものである。それに対し吉田氏の著作は、「兵士の目線」を重視し、「兵士の立ち位置」から、凄惨な戦場の現実を捉え直しており、ミリタリーファン向けの本とは一線を画す。
太平洋戦争において日本軍は制海・制空権を次第に喪失し、補給を維持できなくなった。その結果として、多数の日本軍兵士が食糧不足により戦病死(餓死)したことは良く知られている。そうした兵士たちの苛酷な環境を、戦場での覚醒剤使用から軍靴の劣悪化まで、あらゆる側面から具体的に明らかにしたところに本書の特徴が認められよう。
『日本軍兵士』のような、社会史や民衆史の視点から戦争や軍隊を捉え直す研究は、日本のアカデミズムでは決して珍しくなく、むしろ純粋な軍事史の観点から戦争を論じたものより好まれる。しかし一般読者にとっては馴染みにくいテーマであり、本書のヒットは意外に感じられた。太平洋戦争に対する一般読者の知的関心の高まりを象徴する現象と言えよう。
記憶に新しいヒットとしては、麻田雅文『日ソ戦争 帝国日本最後の戦い』(中公新書、2024年)が挙げられる。太平洋戦争というと、日本は専らアメリカと戦っていたというイメージが強いが、近年はアメリカ以外との戦争に注目が集まっている。
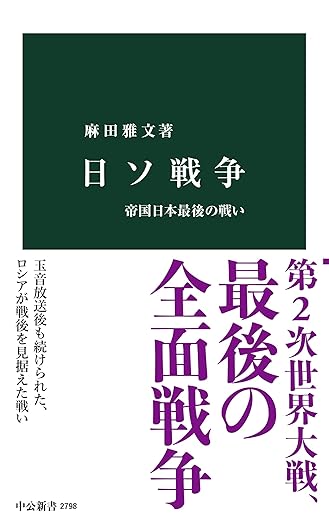
広中一成『後期日中戦争 太平洋戦争下の中国戦線』(角川新書、2021年)もそうした視点からの意欲作であるが、『日ソ戦争』はさらに大きな話題を呼んだ。同書の商業的成功は、もちろん同書の内容的充実を前提としているが、ロシアが突如としてウクライナを侵略し、残虐な殺戮・暴行を繰り返しているという現状において、ソ連(ロシア)の軍事文化への関心が高まったことが背景にあるのだろう。










































