このような「体内でビタミンCを作れない」という性質は、一見デメリットしかないように思えます。
そしてデメリットしかない変異ならば、そのような変異を起こした個体は自然淘汰によって排除され、人類はビタミンCを自前で合成する能力を保っていたはずです。
ではなぜ進化の中でこのような不利な変化が起きたのでしょうか?
従来は「果物を多く食べるようになったためビタミンC合成能力が不要になり、たまたま失われた」という説が一般的でした。
しかし現在の恵まれた食生活の中でも私たちはしばしばビタミンC不足を起こし健康を害することもあります。
6000万年以上前の先祖たちについても、せっかく持っていたビタミンCの合成能力を失うという進化を起こした理由を「単に果物を沢山食べていた」で済ますのは、やや説明として弱い部分があります。
そこで今回研究者たちは、ビタミンCを体内で合成できなくなるという進化に「何らかの隠れたメリットがあるのではないか?」と考えました。
そこで注目したのが寄生性の病原体との関係でした。
例えば熱帯病の一種である住血吸虫(じゅうけつきゅうちゅう)は、毎年2億5千万人以上を苦しめる深刻な寄生虫病で、血管内に住みついて毎日数百~数千個もの卵を産みつけます。
産まれた卵は宿主の臓器に詰まって炎症を起こし、慢性的な病気(住血吸虫症)につながります。
ですが当の住血吸虫自身はビタミンCを合成できないため、必要なビタミンCはすべて宿主から補給しなければなりません。
そのため研究者たちは、「ビタミンC欠乏が寄生虫の繁殖を妨げ、宿主を守っているのではないか?」という大胆な仮説を立て、検証を行うことにしました。
なぜ進化の途中でビタミンCを作る力が失われたのか?
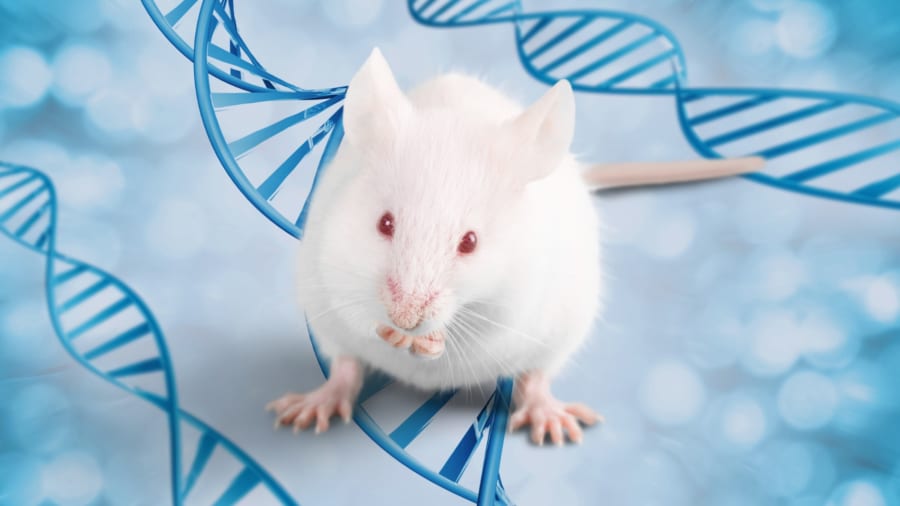
研究ではまず、人間と同じくビタミンCを自分で作れないマウスを用意しました。
このマウスは、エサからビタミンCをとらなければ欠乏症(壊血病のような症状)になります。














































