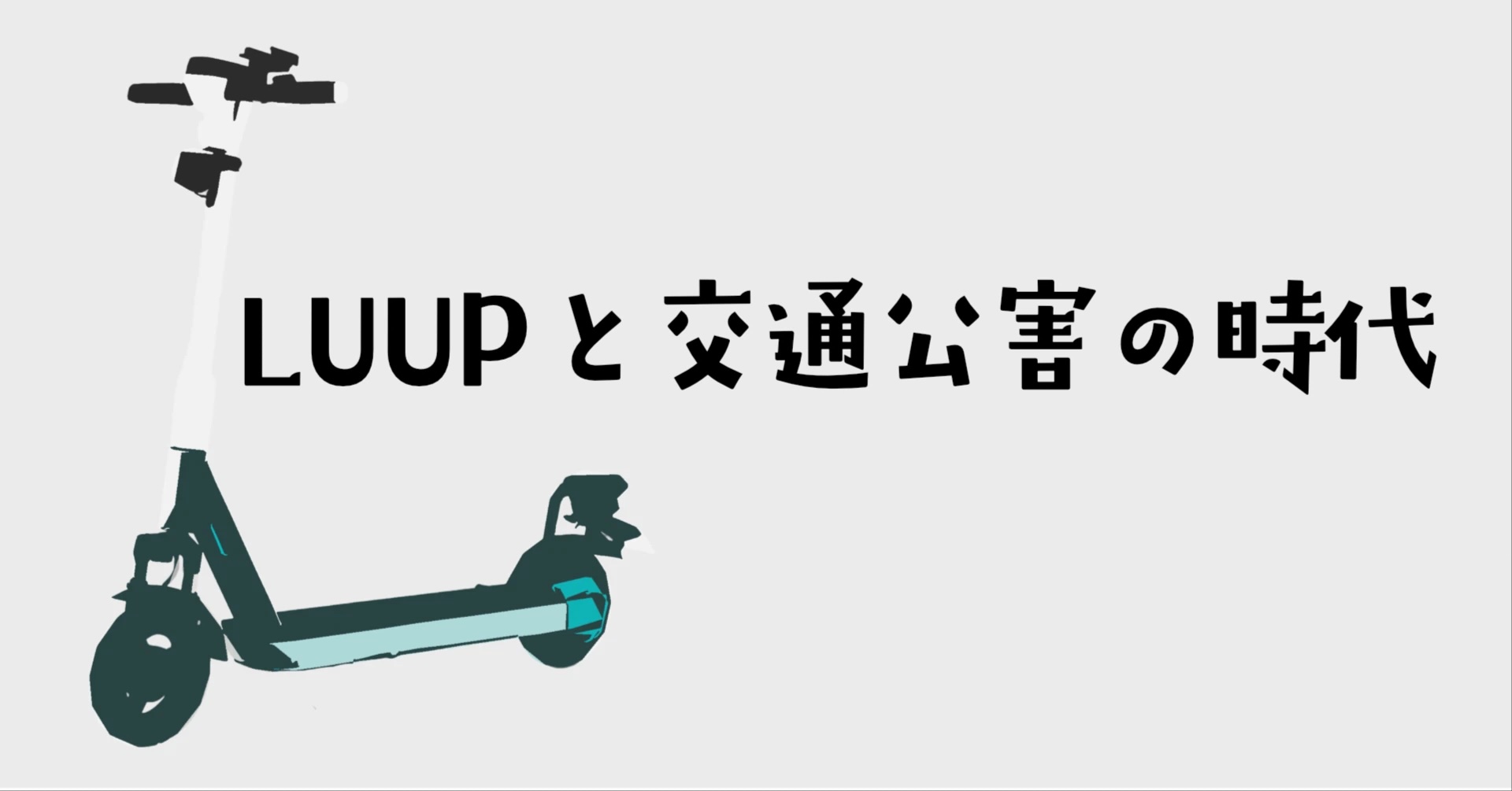
ゴジラ対ヘドラの時代
ゴジラ映画の中で、もっとも忘れ難い怪獣はヘドラだ。
駿河湾を汚染していたヘドロを食べて成長した怪獣が印象的だったのは、後に私と両親が暮らすことになる祖父母の家が静岡県にあり、田子の浦周辺を通りかかるたび悪臭を嗅いでいたからである。
1970年代は、怪獣映画のテーマに取り上げられるほど、日本国中が公害に悩まされていた時代だった。汚れていたのは田子の浦だけではない。河川は泡立ち、大気汚染によって喘息を患う人が珍しくなかった。
当時は現在より工業廃水や排気を浄化する技術が劣っていたのは間違いない。しかし、公害が深刻化した理由はこれだけではない。1950年代から水俣病やイタイイタイ病や四日市ぜんそくが問題視されていたにもかかわらず、社会的責任に対する企業の倫理観が低かっただけでなく、政治が解決すべき優先課題として公害問題に取り組むのが遅れた。
ようやく1970年に公害対策本部が内閣に設置され、公害対策本部を発展する形で環境庁が1971年に発足すると対策が進み、80年代になると海や大気はだいぶきれいになった。
いま田子の浦は、現代的な景観を除けば「田子の浦にうち出でて見れば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ」と歌われた時代の美しさを取り戻している。公害の時代だった1970年代を知らない人にとっては、きっと映画『ゴジラ隊ヘドラ』の内容は荒唐無稽すぎて理解できないだろう。公害問題を解決した私たちは、努力をもっと誇るべきではないか。
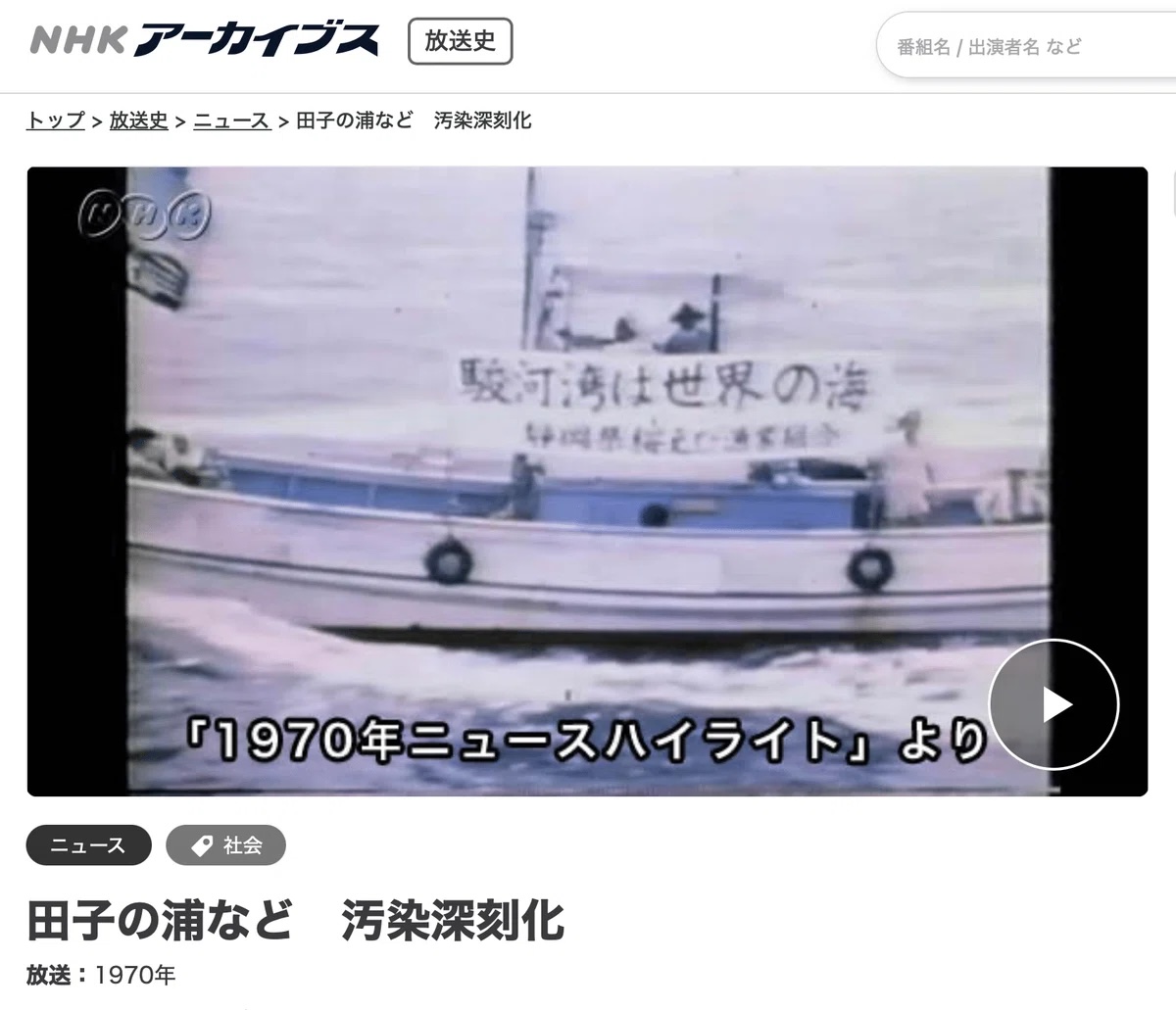
参考映像/田子の浦など 汚染深刻化NHKより
LUUPと交通公害の時代
前置きが長くなってしまった。
公害とは、経済合理性の追求を目的とした社会・経済活動によって公共にもたらされる害だ。だから私は、株式会社Luupが行っている電動キックボートのシェアリングサービスは「公害」で、同社は公害企業だと位置付けている。
Luup社が電動キックボードのシェアリングサービスを開始すると、たちまち不安を語る声が市中にあふれた。なぜなら諸外国で電動キックボードの公道走行が迷惑がられ、路上から排除されつつあったからだ。







































