こうした技術を使い、研究チームは最大45×45=2025個の場所のうち2024個という、ほぼ穴のない原子配列を作ることに成功しました。
さらに、723個の原子で大学名「USTC」の文字を描いたり、自由な形やパターンも再現できることを実際に示しています。
また、最大549個の原子を使って「シュレディンガーの猫」のイラストを“動画”のように再現することもできました。
この猫動画は、原子の配置が次々と切り替わる様子を33倍にスロー再生したもので、本当は私たちの目では追いつけないほど速い変化が起きているのです。
さらにこの技術は、平面だけでなく立体的な配列にも応用されています。
研究チームは原子を3層に積み上げて、まるでレゴブロックのような直方体の立体構造を作りました。
このとき、層をまたいで原子を移動させると損失が増えるため、基本的には各層ごとに原子を動かす工夫をしています。
例えば、19×19の正方形を3段重ねた配列では、1083個中1077個という高精度な3D配列ができました。
また、最近話題になっている「ツイスト・グラフェン(ねじれたグラフェン)」という新しい物質構造も再現されています。
これは、3層の原子のシートをそれぞれ少しずつ回転させて重ねることで、縞模様(モアレ模様)が現れる仕組みです。
研究チームは、このパターンを752個の原子で見事に作り上げており(756個中4個だけ欠け)、どんな複雑な形でも思い通りに作れる技術だということを証明しています。
量子コンピュータ時代の基盤技術へ
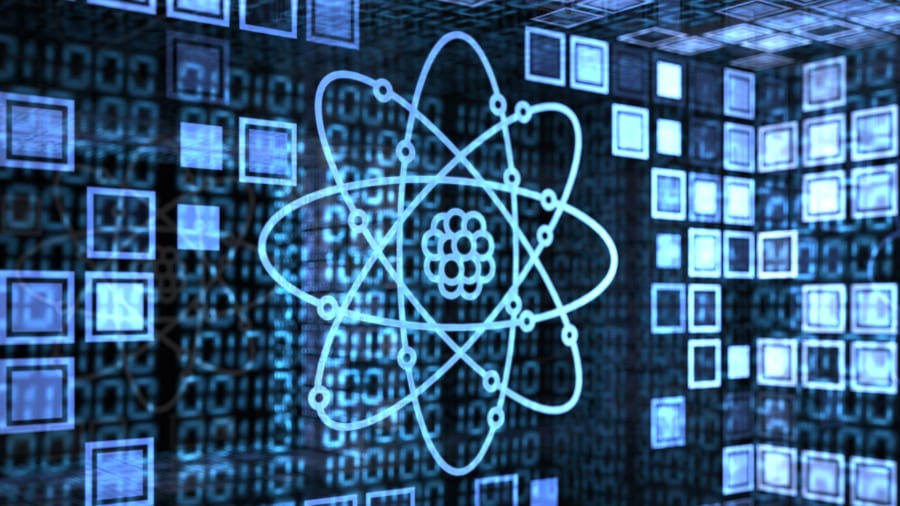
今回の成果は、量子コンピュータの実現に向けた基盤技術として非常に重要です。
なぜなら、量子コンピュータを動かすには大量の原子(量子ビット)が必要ですが、それらを高い品質で素早く用意する手段がこれまで限られていたからです。
開発されたAI駆動のホログラフィック移動法を使えば、必要な数千個規模の原子を一瞬で所定の配置に揃えることができます。











































