教養はなんの役に立つかというと、周りに誇示してマウントを取るためではなく、対象を常に「なにか」と並べて見ることで信者化を回避する、知の予防接種になる点に意義がある。改めてそんなことを、先月刊の『文藝春秋』8月号に片山杜秀先生が寄せてくれた、拙著の書評に感じた。
太宰治。本書に繰り返し現れる。試金石か、リトマス試験紙か。江藤淳と加藤典洋。2人の文芸批評家の個性が、太宰観の相異から、よく浮かび上がるのだ。 (中 略) 江藤が力の出てこぬ弱いセンチメンタリズムと観たものが、加藤においては、懐の深くて形なく底さえない大器に変ずる。
はて、著者は加藤と江藤のどちらに思い入れるか。加藤であろう。
(リンク先で全文が読めます)
見抜かれたかぁー……はさて措き、太宰を「江藤と加藤のあいだ」に置くことで、両者の違いが見える。そんな筆致を採る著者(與那覇)の目論見が相対化されたとき、評者の片山さんと私との異同も姿を現わす、素敵な書評になっている。
私はともかく、太宰にせよ、江藤にせよ、加藤にせよ(あと片山さんにせよ)、熱心なファンが多い。それ自体はいいことだけど、対位法のように組み合わせることで、誰かのファンやアンチにならずとも、彼らの作品を味わいやすくなる。
本来「歴史を書く」とは、そんな空間を作る営みだった。歴史をどの程度、誰か(たとえば指導者)を絶対視せずに語れるかが、国や社会の「自由の目安」になるのは、そのためである。
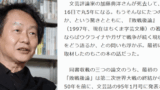
歴史と民主主義の戦いでは、民主主義に支援せよ: 30年目の「敗戦後論」|Yonaha Jun
3/10の毎日新聞・夕刊に、川名壮志記者によるロング・インタビューを載せていただいています。先ほど、有料ですがWeb版も出ました。
特集ワイド:昭和100年 平成はどこへ 消えた「時代の刷新」 與那覇潤さんに聞く | 毎日新聞 歴史軸を失った私たち ちまたでは「昭和100年」が話題になるが、へそ曲がりなの...
特集ワイド:昭和100年 平成はどこへ 消えた「時代の刷新」 與那覇潤さんに聞く | 毎日新聞 歴史軸を失った私たち ちまたでは「昭和100年」が話題になるが、へそ曲がりなの...










































