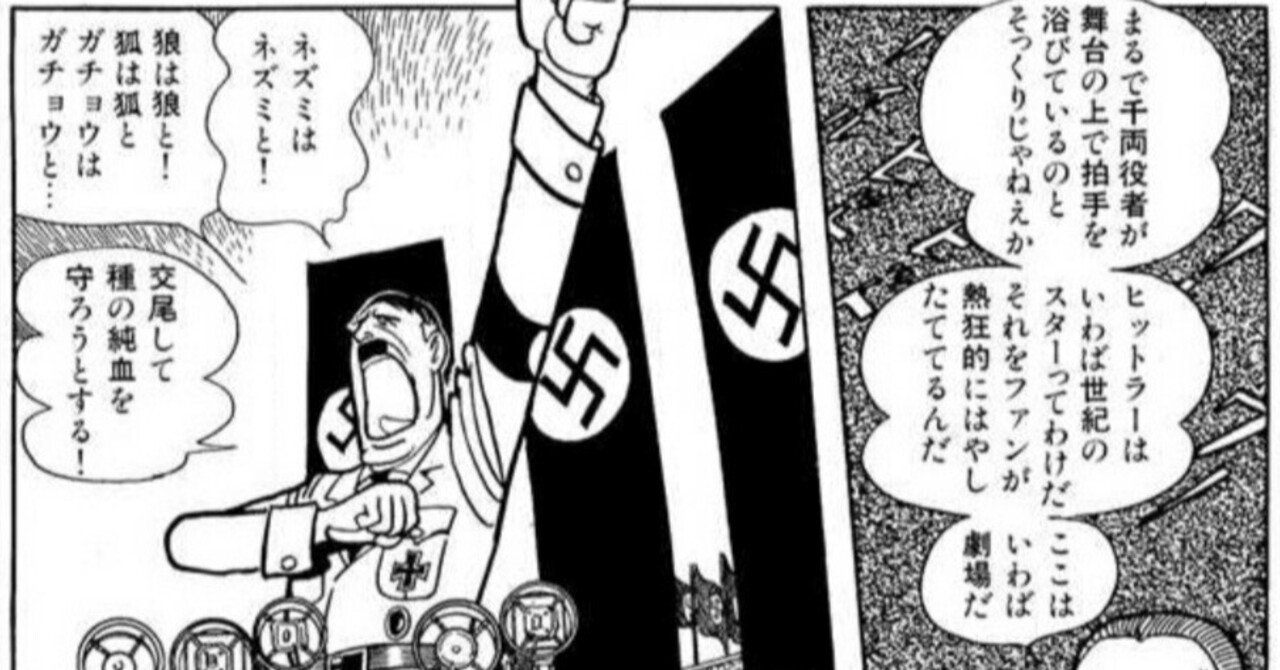
6月末に行った『江藤淳と加藤典洋』のイベントの、冒頭30分がYouTubeで公開されたほか、ダイジェストがデイリー新潮の記事になった。まずは聞き手と文章化を務めてくれた山内宏泰さん、ありがとうございます。
で、自分で言うのはなんだけど、「なんでふたり採り上げたんですか?」という問いに答えて、結構いいことを話してる気がした。
江藤と加藤や、彼らの専門だった「文学」に興味がなくても、それって今日すごく大事な姿勢になっていると思うのだ。なぜなら――
ひとりのみを取り上げてものを書くと、どうしても対象に没入することとなります。たとえば江藤淳だけを取り上げた場合、「江藤淳、推し」となるか、逆にものすごくアンチに振って全面否定するか、になりがちです。
「僕はこの点は江藤さんのほうに近い、でも別の点では、むしろ加藤さんのほうに説得力を感じる」のように、江藤と加藤を並べることで、推しかアンチかの両極に行くことなく、対象と適切な距離を保つスタイルが提唱できるんじゃないか。
段落を改変し、強調を付与
そう。「ひとりだけ」しか眼中にない状態は、その人を褒める(推し)にせよ、貶す(アンチ)にせよ、健康でない。褒める/貶すにも「他の人と比べてどうか」という指標が要るはずが、スキップしがちになる。
それでも歴史が生きていたうちは、まだよかった。数十から数百年の時間に濾過されて「この辺はまちがいない」として残った古典から、ひとりを選べば、一定の水準は保証された。私淑するにせよ、乗り越えてゆくにせよ。
ところが歴史が消え、昔話は要らない、とにかく「いまはコロナ、ウクライナ!」なノリだと、そんなセレクションは働かない。で、たまたまTVに映った1名を権威だと錯覚し、ひな鳥のようについてゆく刷り込みが起きる。










































