これにより教師は二つの表記法を同時に扱わざるを得ず、混乱が広がりました。
さらに、多くの元学習者が口をそろえて語るのは綴りの困難さです。
元生徒のジュディス・ロフヘイゲンさんは、「英語が大好きだったのに、綴りができないことが一生の劣等感になった」と話します。
そしてITAの影響をずっと受けている人もいます。
現在58歳になるマイク・アルダーさんもITAの教育を受けた一人です。
彼は電気設備の技術者として働いていますが、スペルミスは日々の課題となっており、次のように述べています。
「スペルチェック機能にいつも頼っています。
今日メールを送ったのですが、単語の15~20%に赤い下線(訂正線)が引かれていました」
また標準アルファベットへの移行に対してショックを受けた生徒も少なくありません。
その一人である元生徒マイク・オールダーさんは、「ある日突然、『今までのは間違いだった』と告げられ、裏切られた気持ちになった」と語っています。
これらの証言は、単なる学習上の課題だけでなく、心理的なダメージも伴っていたことを示しています。
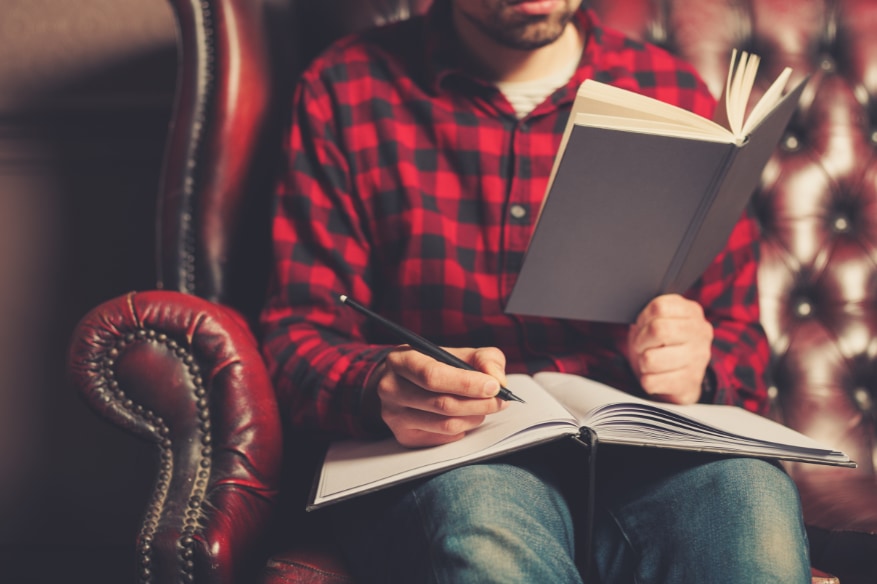
一方で、研究者の中には「ITAが綴り能力に悪影響を与えたと証明する十分な証拠はない」とする声もあります。
綴りの習熟度は教師の質や家庭環境、個人の資質など多くの要因に左右されるため、ITAだけを原因と断定するのは難しいというのです。
しかし、共通して指摘されるのは検証不足です。
これほど大規模に導入されたにもかかわらず、全国的な長期追跡調査や正式な評価報告は存在しません。
失敗の原因や成功事例の分析も行われず、政策的な「教訓」として体系化されないまま終了してしまったのです。
1960年代に誕生した「ITA」は、1970年代年代にはほとんど使用されなり、今ではその存在を知っている人も少なくなりました。











































