つまり、意外なほど良い体験、すなわちポジティブな驚きが相手の脳に学習と行動変容を促すのです。

もう一つの重要な仕組みは、主観的な情報価値(Subjective Value of Information:SVOI)です。
これは、どれだけ正しい情報でも「自分と関係ない」と感じると、脳がその情報に価値を認識しなくなるというものです。
自分の目標やアイデンティティに合う情報であれば、脳はそれを高く評価します。
逆に、自分に無関係だと感じる情報は、脳にとって無意味なものとして処理されてしまいます。
SharotとGarrettの2016年の研究によれば、主観的価値が高い情報は脳の報酬系が強く反応することが明らかになっています。
つまり、ただ正しい情報を提示するだけでなく、それが相手にとって意味のあるものであることが重要なのです。
この2つの仕組みを理解することで、よくある論破や否定、恐怖喚起といった説得法が、なぜ逆効果になるのかがわかってきます。
「失敗する説得」と「成功する説得」の違いは?
ホフマン博士は、多くの広告や政治キャンペーン、医療メッセージが脅しや否定に依存していると指摘しています。
たとえば、「あいつに投票すれば生活が破滅する」といった政治広告や、「タバコを吸えばがんになる。財布も臭いも最悪だ」といった健康警告、「地球温暖化が進めば世界は滅びる」といった環境メッセージです。
これらは確かに事実かもしれませんが、脳の恐怖回避装置である扁桃体が作動し、学習や変化を拒絶する状態になってしまいます。
その結果、「怖いから聞きたくない」「うるさいから無視したい」と思わせてしまい、説得が失敗してしまうのです。
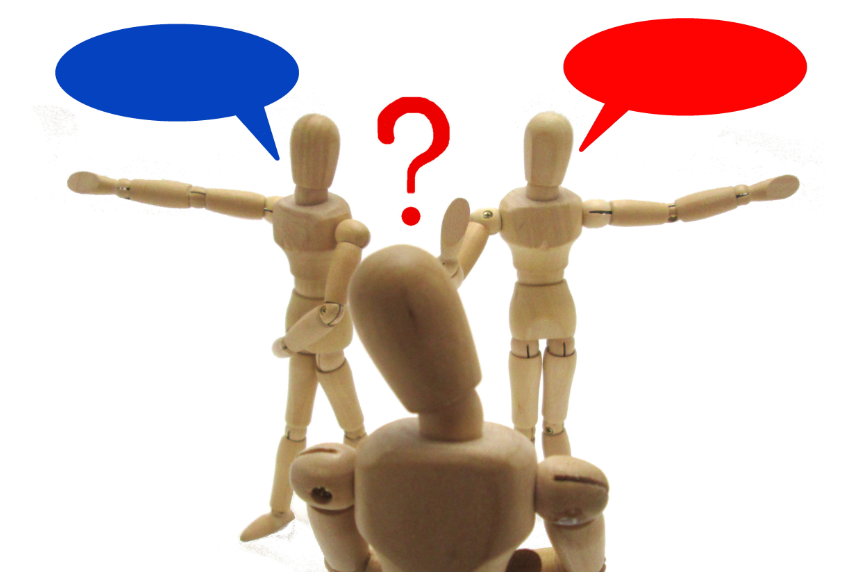
では、どうすれば脳が耳を傾けてくれるのでしょうか。











































