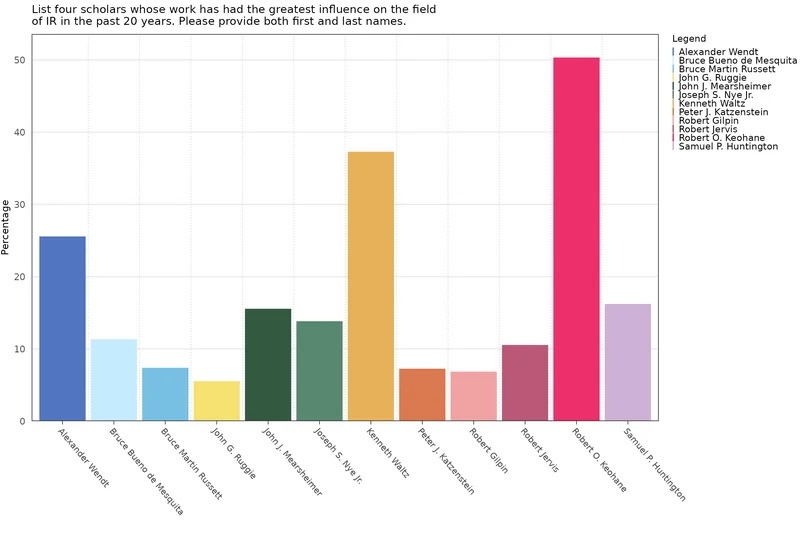
他方、ネオリアリズムと呼ばれるウォルツの理論は、さまざまな研究者から、その限界や予測に対する反証が提示されています。では、われわれは彼の国際政治の理論をどう評価すべきでしょうか。
『国際政治の理論』の訳者である岡垣知子氏(獨協大学)は、「訳者あとがき」で次のように述べています。
「ウォルツは、理論的な敷居を突破した者のみが知っている美しい世界と科学的研究の醍醐味を示すことによって、国際政治学に新しい学問的知見を開いた」
同訳書、282ページ
この「美しさ」とか「醍醐味」といった価値観で科学の理論を評価することには、多くの社会科学者がためらいを感じることでしょう。そのような主観的な物差しではなく、客観的なデータによる実証や反証こそが、科学における理論を評価する基準であると。
そして、国際関係研究では、ウォルツの理論は、その予測が観察に合致しないので、「棄却」「否定」されたという見解も示されています。ウォルツ自身が、二極システムの持続性を予測していたにもかかわらず、冷戦があっけなく終了したではないか。ネオリアリズムは、もはや過去の理論だと。
科学における「美しさ」の重要性
では、そもそも社会科学であれ自然科学であれ、「科学」は実証的証拠により、理路整然と理論が選択されてきたのでしょうか。実は、そうでもないようです。
科学史において大反響を呼んだ話題の書物、スティーヴン・ワインバーグ『科学の発見』(赤根洋子訳、文藝春秋、2016年)によれば、科学の中の科学たる物理学において、「理論の美しさ」は、とても重要な要因であると指摘されています。
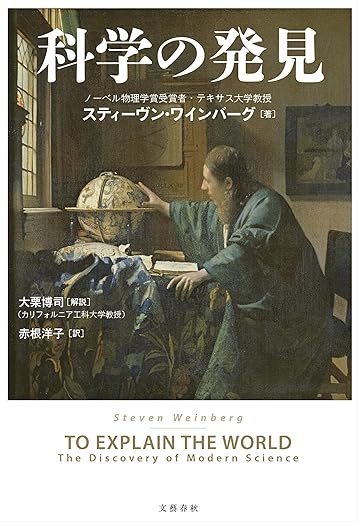
やや長くなりますが、『科学の発見』から引用します。
「コペルニクスの理論は、実証的証拠の裏付けを持たない理論が美的基準によって選択され得ることを示した古典的な例である。…コペルニクスの主張は単に、『プトレマイオス説の奇妙な点の多くが地球の自転と公転によって一挙に説明できるし、惑星の並び順とそれぞれの軌道の大きさに関して、プトレマイオス説よりもコペルニクス説のほうが遥かに明快である』ということに過ぎなかった。…物理学の歴史に繰り返し現れるもう一つのテーマ―観察結果にかなりよく合うシンプルで美しい理論は往々にして、観察結果にさらによく合う複雑で醜い理論よりも真実に近い―の実例である」









































