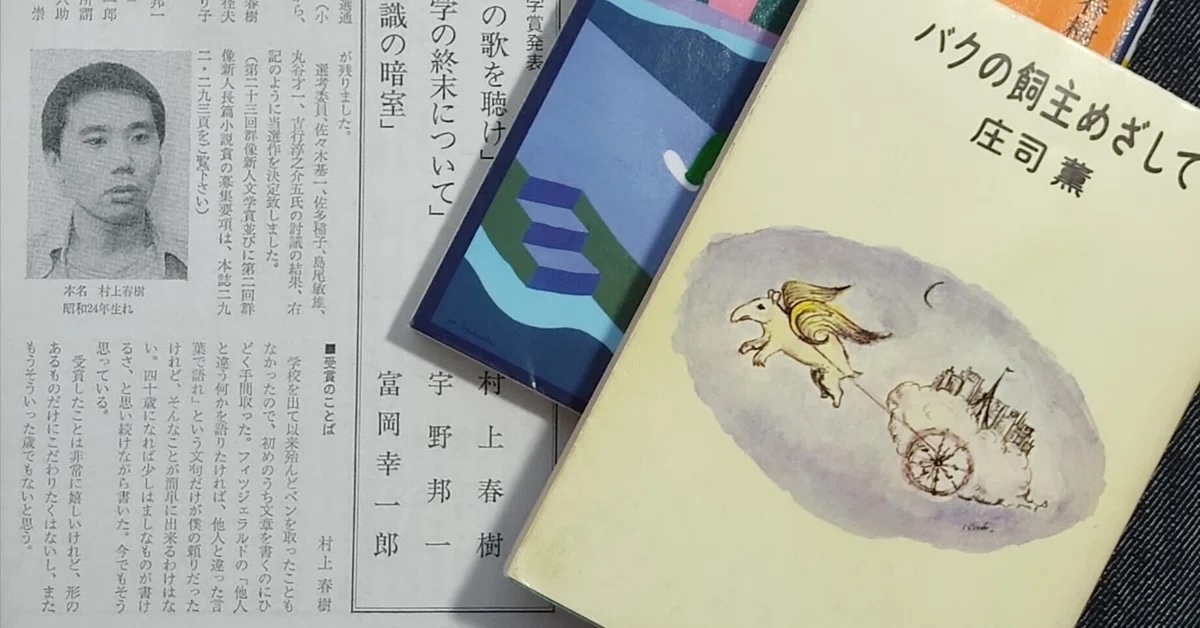
5月以来、毎日のように『江藤淳と加藤典洋』の宣伝ばかり考えて送る夏なのだが、ネットで嬉しい感想を見つけてしまった。7/22の投稿で、書いてくれたのは画家ないし絵師の人らしい。
嬉しいと言っても、別に「うおおおおこれが戦後批評の正嫡! ひとり勝ち! 著者には批評の覇王をめざしてほしいッ!」みたく持ち上げてるわけじゃない。むしろ拙著への違和感を踏まえつつ、その由来を掘り下げてゆく書き方が、「なるほどなぁ」と感じて気持ちよかった。
著者が歴史学を捨てて転身してきた文芸の現在は、江藤淳と加藤典洋が拘ってきた「捻じれ」をどのように表象しているのだろう? (中 略) この〔近年に芥川賞を取るような〕世代の書き手にとって<国>はもはや自明の<ホームランド>ではないと思える。<国>という概念ではなく、人種を超えた文化的な同族意識、自己の属する文化的コミュニティを<ホーム>であると思っているのではないだろうか。 (中 略) そんな軽々と国境を越えていく者と、今や無効となりつつある<国>という概念の内側に閉じこもろうとする者の差異が露わになった時代なのだろう。前の世代の業績や成果を無にしないとするならば、著者の取り上げる文芸作品の間口を広くしてアップデートした次回作を読んでみたい。
村田沙耶香さんとか、どのように長い長い戦後史の中に定位できるのか? 聞いてみたいものだ。
段落を改変し、強調を付与
江藤や加藤は、日本という〈国〉と自分との関係がしっくりこないことから出発し、その原因を戦前と戦後のあいだで生じた「ねじれ」に求めた。でも、〈国〉とか興味ないっすよ、そんなの自分とカンケーない場所なんで、意識しないッス、な感覚で書かれる小説にとっては、そうした論じ方こそしっくり来ないのかもしれない。











































