第2の理由は、産業と農業の機械化です。
西部馬脳炎ウイルス(WEEV)が何度も流行した20世紀初頭では、産業や農業で馬が重要な役割を果たしており、どの農場にも馬小屋があって、多くの馬が密度が高い環境で飼われていました。
そして馬たちの傍には馬と密に接する人間がたくさんいました。
しかし産業や農業が機械化すると、馬そのものの需要が減り、馬と密に接する人間も減っていきました。
人間からすれば馬から機械への切り替えに過ぎませんが、ウイルスにしてみれば、北米のあらゆる地域で主な宿主たる馬が激減したことになります。
このような宿主の激減も、ウイルスにとっては宿主を別の種に乗り換える動機となります。
特に西部馬脳炎ウイルス(WEEV)は進化速度の速いウイルスであるため、環境の変化に敏感に反応できます。
そのため研究者たちは、西部馬脳炎ウイルス(WEEV)は認識する対象を変化させることで、人間や馬以外の種を宿主にしたと述べています。
では、人類はもう西部馬脳炎ウイルス(WEEV)に悩まなくてもいいのでしょうか?
ウイルスは常に進化するため「絶対」はない
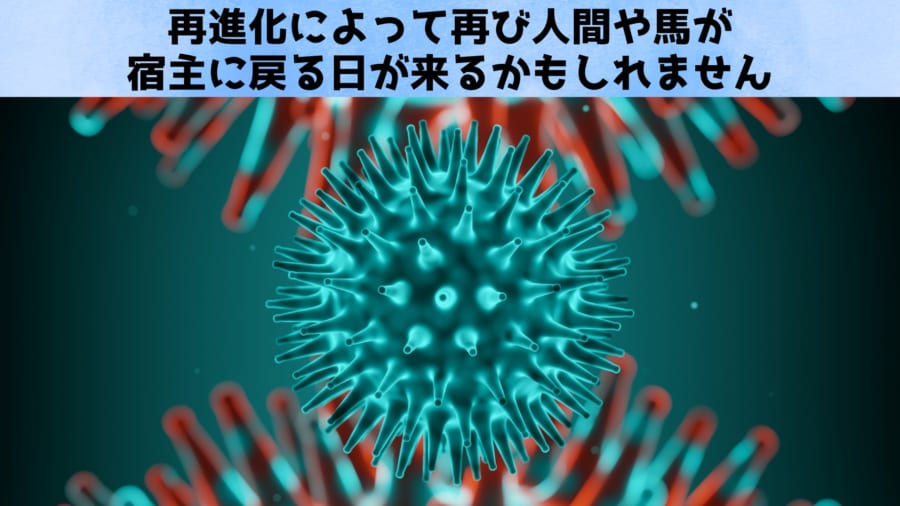
哺乳類から手を引いた西部馬脳炎ウイルス(WEEV)は、もう安全なのか?
残念ながらそう簡単なわけではないようです。
今回の研究は、ウイルスの感染システムが常に揺れ動いており、大流行を起こせた宿主でさえも容易に見切りをつけれるほど、柔軟であることを示しています。
実際、西部馬脳炎ウイルス(WEEV)は今でも鳥類や蚊の体内にも存在し続けていると考えられます。
このことは、消えたと思っていた危険なウイルスたちが、実は宿主を変えて「潜伏」しているに過ぎないことを示しています。
ウイルスの早い進化速度を考えると、再び哺乳類での流行を引き起こすのは時間の問題と言えます。
一方、現在の標準的なウイルス学では、研究者たちは限られた宿主を対象にした限られたウイルス株しか調べません。













































