そっと触れられただけなのに、鋭くはっきりと感じることもあれば、逆に同じ刺激がほとんど気にならないこともあります。
このムラのある感覚は決して気のせいではなく、脳内にある仕組みによって生じる現象だとする研究結果が発表されました。
スイス・ジュネーブ大学の研究チームは、脳の視床と呼ばれる部位が単に感覚信号を中継するだけでなく、まるで「感度を調節するダイヤル」のように働いていることを明らかにしました。
私たちが感じる感覚の強さは、単なる注意力や心理的な状態によって変化しているわけではなく、実は脳の「視床」という部位が、まるで感覚の強さを調節するダイヤルのように働き、皮質のニューロンの感受性を細かく調整していることが明らかになったのです。
その結果、必要なときだけ感覚を敏感モードに切り替え、不要な情報は鈍感モードでスルーできるという、人間の巧みな感覚調節が実現していました。
今回の発見は、自閉症スペクトラム障害の感覚異常や意識状態の調整メカニズムの理解にも重要なヒントを与えるものです。
しかし視床がどのようにして「特定のニューロンだけ」を選んで感覚調節を行っているのか、その詳細な仕組みとは一体どのようなものなのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月1日に『Nature Communications』にて発表されました。
目次
- 感覚の『揺らぎ』はなぜ起こる?脳科学が迫った長年の謎
- 脳の中にあった感覚の『ボリューム調整つまみ』
- 視床と感覚調整の謎が解けた!自閉症や意識の理解にも光
感覚の『揺らぎ』はなぜ起こる?脳科学が迫った長年の謎
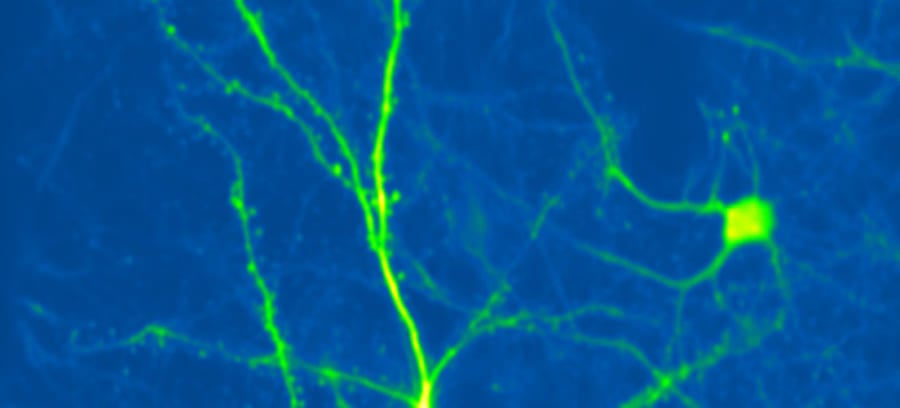
私たちは普段の生活の中で、さまざまな感覚に無意識のうちに包まれています。
たとえば静かな夜に横になっていると、時計の「カチ、カチ」という小さな音がやけに気になって眠れないことがあるでしょう。











































