あっ! 軍国主義の時代は、「防諜ごっこ」も少国民に流行りました。「噂ではあの家はスパイ~」「ボクらも戦ってるぞ!」みたいな。で、民主主義の選挙でも同じことやってる大きな少国民をこの前見たけど、なにしてんの。戦争のコスプレ?

選挙の情勢を「外国のせい」にする人こそ、民主主義の脅威である。|與那覇潤の論説Bistro
今年の1月に出た『文藝春秋』では、浜崎洋介さんとこんな議論をした。2024年末にルーマニアで極右候補が躍進した大統領選挙を、「ロシアの工作だ」として無効にする事件を受けてのことだ。
浜崎 外国からの政治干渉というのは、政治的には当たり前の話ですよ。だから干渉されないように防衛するんですが、でも、実施された選挙自体...
進歩のない人たちで「遊ぶ」のはこの辺にして、先ほどの引用で大事なのは、最後の1行です。
しかしそうなるのにも、理由がある。
前も書いたけど、批判と非難は別のもので、どこで分かれるか。単にダメ出しして満足なら、非難。「しかしなぜそうなった?」と理由まで考えるのが、批判というのは、妥当な指標でしょう。
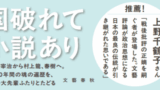
言論人にとって「批判」とはなにか?:『江藤淳と加藤典洋』刊行によせて|與那覇潤の論説Bistro
いよいよ本日(5/15)、新刊『江藤淳と加藤典洋』が発売になる。ヘッダーのとおり、上野千鶴子さんが、過分な帯を寄せてくださった。 ……と、殊勝なことを書くと「口先だけで、お前ホントは恐縮してないだろ?」とか絡む人が出てくるけど、そんな次元の話ではない。
二人の巨人と辿る戦後80年間の魂の遍歴 『江藤淳と加藤典...
二人の巨人と辿る戦後80年間の魂の遍歴 『江藤淳と加藤典...
なぜ80年近く後にウクライナ戦争を迎えても、日本の民度は真珠湾攻撃に沸く「少国民」のままだったのか。その考察は『Wedge』を手に取っていただくとして、書ききれなかった小林さんの挿話を、最後にご紹介したく。
小林信彦さんの『一少年の観た〈聖戦〉』は、1940年11月の「皇紀2600年祭」に始まり、47年5月3日の日本国憲法施行の式典で終わります。あいだに挟まる「戦争」の熱狂と、幻滅を経て――







































