
Warchi/iStock
(前回:『少子化する高齢社会』の「縁、運、根」)
サバティカル制度
私の北大勤務時代に、文系学部でもいわゆる「サバティカル制度」が始まった。これは欧米の大学では古い歴史を持つ制度であり、通常は7年に一度、半年もしくは1年間の「研究・休息・旅行」のために与えられる有給休暇を指している。原語はsabbath(安息日)であり、そこから派生してsabbatical yearとして世界的にも広く使われている。
2000年の大学院大学改革を踏まえて、北大でもその導入が検討されて、2007年から施行された。文学研究科でも前年に半年間の「サバティカル制度」募集があり、数名が応募した結果、勤務歴23年の私が教授会で選ばれたのである。
半年間、講義・ゼミ・会議・学位認定すべてを免除
これは大学教員にとっては大変画期的な制度であり、2007年度前期を私はサバティカル期間に当てた。
学部としては、後期は入試業務があるために、非公式ながらできるだけ前期にしてほしいという要望があったように記憶している。何しろ研究室に出ても、旅行に行っても、調査に出かけてもいいのだから、自由な時間が最大限活用できた。本書はその半年間の成果の一つである(写真)。
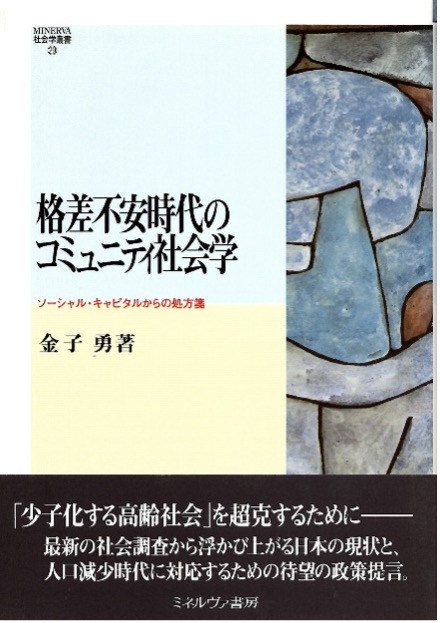
サバティカル期間の成果
すなわち、本書の原稿をこの期間に集中的にまとめたのであるが、前々回の連載に紹介した『社会調査から見た少子高齢社会』の続編にあたる内容になっている。この時代の10年間は社会調査に明け暮れていたとそこでも述懐したが、日本国内でも助手と院生数名、学生20名を伴い、鹿児島市、宜野湾市、富良野市、伊達市、白老町の訪問面接調査を順次行って、膨大なデータを蓄積していた。
ただし、鹿児島市調査は知人の教授に相談して、鹿児島大学の社会学専攻生を20名雇ったし、宜野湾市の調査でも沖縄国際大学教授にお願いして、社会学専攻生を20人紹介していただいた。これも人脈として培ってきた長年の縁を活かせた調査活動になった。もちろん文科省の「科学研究費」基準通りに、学生・院生一人1日での日給8000円はきちんと支払った。






































