斎藤 一般論的な説得は全然ダメで、効果がないんです。ただ「私はあなたに死んでほしくない」と伝えるのは構いません。それは一般論ではなく、本人の心がこもった価値観ですから。 もっとも、いきなり「死んでほしくない」と言っても、そこに共感がなければやっぱり無意味なので、まずは相手の話をしっかり聞いて、共感することが必要です。
『心を病んだらいけないの?』33-4頁
次の本のためにいま勉強してるけど、「ナラティヴ・セラピー」という分野がある。メンタルの病気は外科手術のように、病巣を物理的に切り取る形では治せない。平成に注目された新薬も、当初の期待ほどには効かなかった。
むしろ「このせいで病気になったけど、でもそれを通じて得たものもあるな」のように、本人の物語の一部に病気を位置づけることができたときに、回復が起きる。治療者の側から言えば、最初は病気で「わけわからんことを言う」他者だった当事者を理解することとも、それは一体である。
歴史とは、こうした物語の主語を大きくしたものだ。ぼくたちは時に、「なんで私は」ではなく「なんで日本は」と問わないと、やってられない状況に直面する。その社会に穏当な歴史観があるか、とは、国民が過去に受けた傷と適切につきあえているか、と同義なわけである。
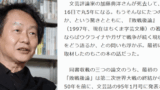
歴史と民主主義の戦いでは、民主主義に支援せよ: 30年目の「敗戦後論」|Yonaha Jun
3/10の毎日新聞・夕刊に、川名壮志記者によるロング・インタビューを載せていただいています。先ほど、有料ですがWeb版も出ました。
特集ワイド:昭和100年 平成はどこへ 消えた「時代の刷新」 與那覇潤さんに聞く | 毎日新聞 歴史軸を失った私たち ちまたでは「昭和100年」が話題になるが、へそ曲がりなの...
特集ワイド:昭和100年 平成はどこへ 消えた「時代の刷新」 與那覇潤さんに聞く | 毎日新聞 歴史軸を失った私たち ちまたでは「昭和100年」が話題になるが、へそ曲がりなの...
とはいえ物語を通じた回復には、時間がかかる。「このストーリーに乗せとけば、誰でもOK」みたいな万能のテンプレは、落ちてない。東畑さんのようなカウンセラーも、利用者から「私の話をわかってない!」と怒られたりして、大変らしい。










































