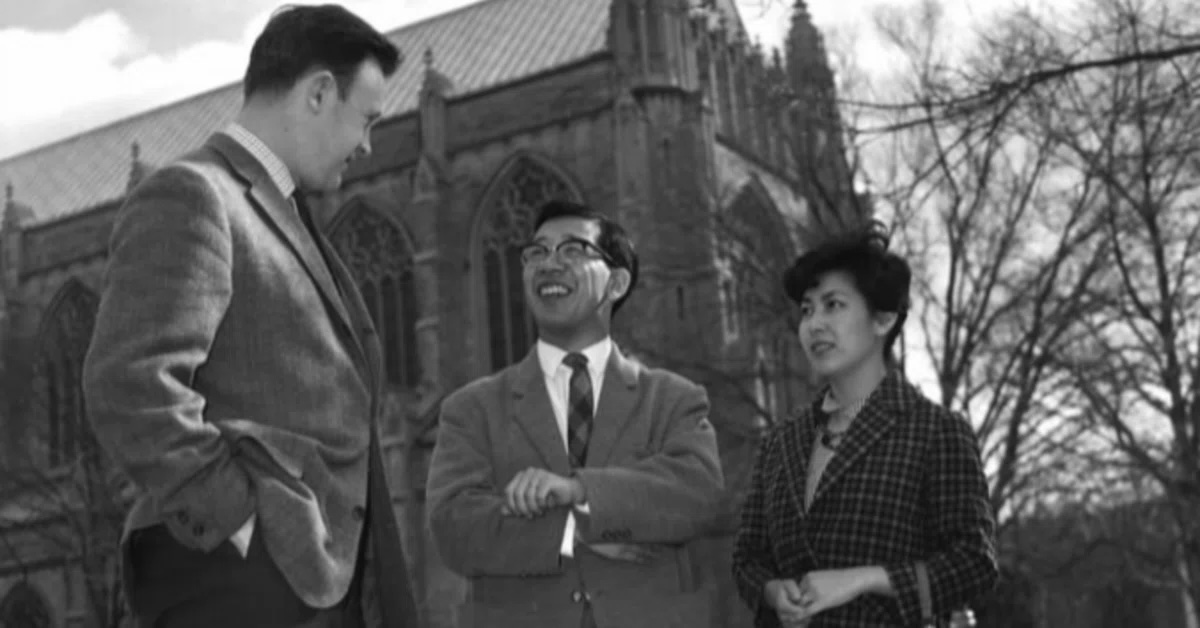
臨床心理士の東畑開人さんが、6/22の読売新聞に『江藤淳と加藤典洋』の書評を書いてくれた。いまは同紙のサイトで、全文が読める。
遠かった昔々が、私とあなたの今の一部になる。そのために、昔と今のあいだを振り返るべく一緒に歩む人が必要である。
それこそが歴史家の仕事であると著者は考えているわけだが、思えばそれは心理療法家が日々の臨床でなしていることでもある。歴史は心を柔らかくし、他者と一緒に居られる強さをくれる。
強調と改行を追加
「遠かった昔々」とは、民俗学が扱う民話の語りを想定した表現だろう。『まんが日本昔ばなし』の世界とも言える。もちろんそこでも、「親孝行は大切だ」といった一般化された教訓は手に入る。
しかし「昔々」で語られるストーリーには日付がない。「おじいさんとおばあさん」以外に名前もない。これだと、物語に個別性が生まれず、一般論ではなく「この私が」なぜこう生きるのかという切実さが伴わない。
たとえばメンタルの相談ごとでは、「もう死にたい」みたいな発言はふつうに出る。そういうときに、一般論で応答しても意味がないことは、前に精神科医の斎藤環さんとも議論した。
與那覇 「親不孝だ」「周りの人が悲しむ」などと説得するのも良くないそうですね。










































