
wildpixel/iStock
現代の外交において、「宥和(appeasement)」ほど悪名高いものはないかもしれません。この汚名の起源は、いうまでもなく「ミュンヘンの教訓」にあります。
ミュンヘン会談において、イギリスのチェンバレン首相は、ナチス・ドイツのヒトラー総統の領土拡張の野心に対抗せず、それを認めてしまいました。そして、このことは不幸な第二次世界大戦の勃発につながりました。その結果、宥和は侵略を助長する悪しき政策であると広く否定されるようになりました。同時に、このような宥和への解釈は、外交において妥協や譲歩は禁物であるという「一般命題」を導きます。
ところが、近代外交において、宥和は肯定的な意味合いを持っていたというと、皆さんは驚くかもしれません。実は19世紀から20世紀の初め頃まで、世界の覇権国であった「大英帝国」は、その基本的な外交戦略において、宥和をしばしば使っていたのです。
そして、大英帝国が長続きした1つの理由は、この宥和政策にあったと主張する有力な研究もあります。それが軍事史の大家であるポール・ケネディ氏(イェール大学)による著書『戦略と外交(Strategy and Diplomacy: 1870-1945)』です。
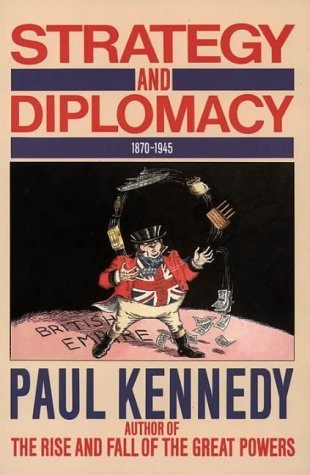
ケネディ氏の著作は、日本でもベスト・セラーを記録した『大国の興亡』(草思社、1993年〔原著1987年〕)が有名ですが、上記書は、専門家以外には、ほとんど知られていないでしょう。『戦略と外交』においてケネディ氏が言いたいことの1つは、大英帝国が宥和政策に支えられていたことです。かれはこう主張しています。
「なぜ帝国はかくも長きにわたり継続したのか…イギリスの大半のエリートの政治文化、すなわち極端を嫌い、理性的な議論に訴え、政治の合理性に信念を抱き、妥協の必要性を認めることは、なぜ大英帝国がそれほど長続きしたのかを説明する、たいへん重要な部分を形成するかもしれない…長い目で見れば、いったん経済的、戦略的潮目が変わってしまった際に、可能な限り世界大の帝国をいかに維持するかにおける根本的問題に関して、この柔軟で理性的で妥協を模索する政策は、断固として『屈服しない』ものより、好ましかったのではないだろうか」










































